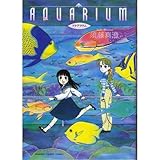2017年09月13日 16:53
薬屋のタバサ≫
カテゴリー │新潮文庫
奇妙な味とよばれるタイプの物語がある。
江戸川乱歩がミステリ小説の中で、それまでのミステリのサブジャンルのどれにも当てはまらないけれどもミステリというおおきな枠としてのジャンルの中の作品には違いない、というかミステリにしておきたいと思ったのだろうけれども、そういった傾向の話に付けた名称なのだが、名称のとおり、読んでみると奇妙な話なのだ。
最近だと、東京創元社から『夜の夢見の川』という奇妙な味の作品ばかりを集めたアンソロジーが出た。
この中で印象に残った作品にエドワード・ブライアントの「ハイウェイ漂泊」という話がある。
通常、奇妙な味の作品の場合、不思議なことが起こる。しかし、「ハイウェイ漂泊」には不思議な事はまったく起こらないのだ。不思議なことはまったく起こらないけれども、読んでいると不安になる。何かおかしなことが物語の中では起こっているのではないかと思わされる。
東直子も奇妙な味の作家だと思う。
『らいほうさんの場所』もそうだったが、この『薬屋のタバサ』も奇妙な味の話なのだ。
なおかつ、物語の中では不思議な事は起こらない。
主人公はとある町にやってきて、そしてその町の薬屋であるタバサ薬局で働くこととなる。タバサというのはその薬局の主の名前だ。
主人公が何故この町にやってきたのかは説明されない。主人公も思い出すことができないようだ。
登場人物達の言動は、何一つ不思議なことは言ってはいないのだが、不穏である。
タバサの薬を飲んだ老人は、それまで寝たきりに近い状態だったけれども、翌日には歩きまわることができるようになる。老人の息子はこれで予定を立てることができると言う。何の予定なのだろうか。
そしてその翌日、老人は亡くなってしまう。
主人公は、タバサが作った薬が原因ではないなと考える。息子の、「予定が立つ」とは死ぬことがわかっていたからではないかと。
しかし、老人の死に不審なところはない。タバサがおかしな薬を与えたわけではない。
元気になった翌日に老人が亡くなったのは偶然にすぎない。という解釈もできるし、その通りである。
何一つ不思議な事は起こらないのだが不穏で、不気味だ。
すべての中心にタバサがいるようで、いない。
そしてタバサ自身も逃れきれない何かに捕らえられたまま、この町で生活をしている。
江戸川乱歩がミステリ小説の中で、それまでのミステリのサブジャンルのどれにも当てはまらないけれどもミステリというおおきな枠としてのジャンルの中の作品には違いない、というかミステリにしておきたいと思ったのだろうけれども、そういった傾向の話に付けた名称なのだが、名称のとおり、読んでみると奇妙な話なのだ。
最近だと、東京創元社から『夜の夢見の川』という奇妙な味の作品ばかりを集めたアンソロジーが出た。
この中で印象に残った作品にエドワード・ブライアントの「ハイウェイ漂泊」という話がある。
通常、奇妙な味の作品の場合、不思議なことが起こる。しかし、「ハイウェイ漂泊」には不思議な事はまったく起こらないのだ。不思議なことはまったく起こらないけれども、読んでいると不安になる。何かおかしなことが物語の中では起こっているのではないかと思わされる。
東直子も奇妙な味の作家だと思う。
『らいほうさんの場所』もそうだったが、この『薬屋のタバサ』も奇妙な味の話なのだ。
なおかつ、物語の中では不思議な事は起こらない。
主人公はとある町にやってきて、そしてその町の薬屋であるタバサ薬局で働くこととなる。タバサというのはその薬局の主の名前だ。
主人公が何故この町にやってきたのかは説明されない。主人公も思い出すことができないようだ。
登場人物達の言動は、何一つ不思議なことは言ってはいないのだが、不穏である。
タバサの薬を飲んだ老人は、それまで寝たきりに近い状態だったけれども、翌日には歩きまわることができるようになる。老人の息子はこれで予定を立てることができると言う。何の予定なのだろうか。
そしてその翌日、老人は亡くなってしまう。
主人公は、タバサが作った薬が原因ではないなと考える。息子の、「予定が立つ」とは死ぬことがわかっていたからではないかと。
しかし、老人の死に不審なところはない。タバサがおかしな薬を与えたわけではない。
元気になった翌日に老人が亡くなったのは偶然にすぎない。という解釈もできるし、その通りである。
何一つ不思議な事は起こらないのだが不穏で、不気味だ。
すべての中心にタバサがいるようで、いない。
そしてタバサ自身も逃れきれない何かに捕らえられたまま、この町で生活をしている。
2017年09月12日 17:48
夜の夢見の川≫
カテゴリー │創元推理文庫
小説を読むのは好きなのだが、結末がすっきりしない物語というのが苦手だ。
なので、本格ミステリやSFといったジャンルの物語を読むことが多い。本格ミステリの場合は謎があるが、それは解かれるべき謎で、物語の最後には全てすっきりと割り切れる。SFの場合は架空論理の構築による物語なので、物語全体が理屈であって、これもまたすっきりとしている。
もちろん、どちらのジャンルにも例外的な物語は存在するのですっきりしない物語もあるのだが、それはそれでそれが全てというわけではないので安心して読むことができる。
それに対して、何がどうなったのかはっきりとしない物語というものが存在する。
江戸川乱歩によって奇妙な味と名付けられた物語たちで、物語の中で起こった出来事は曖昧なまま、読者の判断に委ねられる。
この本に集められた物語も、編者があえてそういう傾向の物語ばかりを集めたということで、読む前から身構えて読むことになった、
が、不思議なことに身構えると逆にすっきりとしなさ加減が気にならなくなり、全編楽しく読むことができた。
もっとも、楽しくと書いたが、実際はそんなに楽しい話ばかりではなく、巻頭の「麻酔」は実に嫌な話で、歯医者に行ったらとんでもない目に遭ってしまったという物語。すっきりしないというよりも、主人公の身の上に降り掛かった出来事のあまりにもの酷さ加減に、読んでいてこちらのほうがむずむすとしてきてしまう。
キット・リードの「お待ち」も嫌な話で、母娘が自動車で旅行に行った先の町でとんでもない目に合う、しかも娘の方だけ、という話。
確かにどちらの話も何故そんな目にあったのかという理由は語られないのですっきりしない話なのだが、主人公が遭わされた出来事は明確なのですっきりとした話だ。それに対してエドワード・ブライアントの「ハイウェイ漂泊」は不思議なことは何も起こらない。全編仄めかしで、何も起こらないけれども、なにか不思議なことが起こっているような錯覚を起こす。いや起きているのかもしれないが、物語の中では描かれない。うまいなあと思う。
なので、本格ミステリやSFといったジャンルの物語を読むことが多い。本格ミステリの場合は謎があるが、それは解かれるべき謎で、物語の最後には全てすっきりと割り切れる。SFの場合は架空論理の構築による物語なので、物語全体が理屈であって、これもまたすっきりとしている。
もちろん、どちらのジャンルにも例外的な物語は存在するのですっきりしない物語もあるのだが、それはそれでそれが全てというわけではないので安心して読むことができる。
それに対して、何がどうなったのかはっきりとしない物語というものが存在する。
江戸川乱歩によって奇妙な味と名付けられた物語たちで、物語の中で起こった出来事は曖昧なまま、読者の判断に委ねられる。
この本に集められた物語も、編者があえてそういう傾向の物語ばかりを集めたということで、読む前から身構えて読むことになった、
が、不思議なことに身構えると逆にすっきりとしなさ加減が気にならなくなり、全編楽しく読むことができた。
もっとも、楽しくと書いたが、実際はそんなに楽しい話ばかりではなく、巻頭の「麻酔」は実に嫌な話で、歯医者に行ったらとんでもない目に遭ってしまったという物語。すっきりしないというよりも、主人公の身の上に降り掛かった出来事のあまりにもの酷さ加減に、読んでいてこちらのほうがむずむすとしてきてしまう。
キット・リードの「お待ち」も嫌な話で、母娘が自動車で旅行に行った先の町でとんでもない目に合う、しかも娘の方だけ、という話。
確かにどちらの話も何故そんな目にあったのかという理由は語られないのですっきりしない話なのだが、主人公が遭わされた出来事は明確なのですっきりとした話だ。それに対してエドワード・ブライアントの「ハイウェイ漂泊」は不思議なことは何も起こらない。全編仄めかしで、何も起こらないけれども、なにか不思議なことが起こっているような錯覚を起こす。いや起きているのかもしれないが、物語の中では描かれない。うまいなあと思う。
2017年07月28日 17:07
来月の気になる本≫
カテゴリー │ホンの話
角川文庫『人間の顔は食べづらい』白井智之
角川文庫『スタープレイヤー』恒川光太郎
講談社文庫『献灯使』多和田葉子
新潮文庫『機巧のイヴ』乾 緑郎
新潮文庫『アメリカン・ウォー 上下』オマル・エル・アッカド
創元推理文庫『花野に眠る 秋葉図書館の四季』森谷明子
創元推理文庫『月明かりの男』ヘレン・マクロイ
創元SF文庫『わたしの本当の子どもたち』ジョー・ウォルトン
ハヤカワ文庫SF『三惑星の探求』コードウェイナー・スミス
ハヤカワ文庫JA『公正的戦闘規範』藤井太洋
ハヤカワ文庫NV『暗殺者の特務 上下』マーク・グリーニー
中公文庫『殺さずにはいられない 小泉喜美子傑作短篇集』小泉喜美子
竹書房文庫『猫SF傑作選 猫は宇宙で丸くなる』シオドア・スタージョン他
文春文庫『注文の多い美術館』門井慶喜
文春文庫『繁栄の昭和』筒井康隆
文春文庫『雪の香り』塩田武士
文遊社『天国の南』ジム・トンプスン
ヒトのクローンを食用目的で培養する未来。なんともおぞましい設定を使いながら、中身はSFでもなくホラーでもなく本格ミステリという白井智之の『人間の顔は食べづらい』が文庫化。
一方でこちらは純然なファンタジーである恒川光太郎の『スタープレイヤー』も文庫化。
多和田葉子の『献灯使』は東日本大震災を彷彿させる設定でありながらいつの時代とも特定しないSFよりの物語。
オマル・エル・アッカドのデビュー作『アメリカン・ウォー 上下』は災厄まみれの、21世紀後半以降の北米を描いた小説。21世紀後半以降というところが気になる設定だ。
森谷明子の『花野に眠る 秋葉図書館の四季』は『れんげ野原のまんなかで』の続編。 秋葉図書館を舞台としたミステリだが、まさか続編が書かれるとは思わなかった。
思わなかったといえば、ジョー・ウォルトンが翻訳されるとは思わなかった。まあ、<ファージング>サーガが2010年、その次の『図書室の魔法』が2014年なので、このくらいの間隔で翻訳されるのであれば珍しいことではないけれども。
ハヤカワ文庫SFからはようやくコードウェイナー・スミスの全短編集最終巻が出る。ひょっとしたら出ないんじゃないかという気もしていたがよかった。
中公文庫からは小泉喜美子の短編集が復刊。小泉喜美子ファンとしては嬉しい限りです。
竹書房文庫からはいきなりの猫SFアンソロジーが出る。かつて扶桑社ミステリーからJ・ダン、G・ドゾワの編集による猫SFアンソロジー『魔法の猫』が出た事があるけれどもあれとは別物なのだろう。
門井慶喜の『注文の多い美術館』は美術探偵シリーズの第三弾。
塩田武士の『雪の香り』は感動必死の純愛ミステリーという謳い文句で、感動必死というのはゲンナリしてしまうのだが、塩田武士の小説は面白いので読むだろう。
文遊社からはジム・トンプスンの『天国の南』が出る。なんか凄いな。
続いて漫画。
秋田書店『イワとニキの新婚旅行』白井弓子
講談社『Pumpkin Scissors(21)』岩永亮太郎
集英社『そしてボクは外道マンになる(1)』平松伸二
集英社『ゴールデンカムイ(11)』野田サトル
小学館『銀の匙 Silver Spoon(14)』荒川弘
講談社『別式(2)』TAGRO
講談社『とんがり帽子のアトリエ(2)』白浜鴎
小学館『月曜日の友達(1)』阿部共実
集英社『ファイアパンチ(6)』藤本タツキ
秋田書店『AIの遺電子(7)』山田胡瓜
KADOKAWA『ダンジョン飯(5)』九井諒子
平松伸二よお前もかといいたくなるけれども、自伝的漫画、『そしてボクは外道マンになる(1)』が単行本化。『ドーベルマン刑事』とか『ブラック・エンジェルズ』を読んでいた身としては期待が大きい。
久しぶりに荒川弘の『銀の匙 Silver Spoon(14)』の新刊が出る。
久しぶりといえば、阿部共実の久しぶりの新作が今度は小学館から出る。小学館に移ってもおそらく今まで通りの阿部共実なのだろうなあ。
角川文庫『スタープレイヤー』恒川光太郎
講談社文庫『献灯使』多和田葉子
新潮文庫『機巧のイヴ』乾 緑郎
新潮文庫『アメリカン・ウォー 上下』オマル・エル・アッカド
創元推理文庫『花野に眠る 秋葉図書館の四季』森谷明子
創元推理文庫『月明かりの男』ヘレン・マクロイ
創元SF文庫『わたしの本当の子どもたち』ジョー・ウォルトン
ハヤカワ文庫SF『三惑星の探求』コードウェイナー・スミス
ハヤカワ文庫JA『公正的戦闘規範』藤井太洋
ハヤカワ文庫NV『暗殺者の特務 上下』マーク・グリーニー
中公文庫『殺さずにはいられない 小泉喜美子傑作短篇集』小泉喜美子
竹書房文庫『猫SF傑作選 猫は宇宙で丸くなる』シオドア・スタージョン他
文春文庫『注文の多い美術館』門井慶喜
文春文庫『繁栄の昭和』筒井康隆
文春文庫『雪の香り』塩田武士
文遊社『天国の南』ジム・トンプスン
ヒトのクローンを食用目的で培養する未来。なんともおぞましい設定を使いながら、中身はSFでもなくホラーでもなく本格ミステリという白井智之の『人間の顔は食べづらい』が文庫化。
一方でこちらは純然なファンタジーである恒川光太郎の『スタープレイヤー』も文庫化。
多和田葉子の『献灯使』は東日本大震災を彷彿させる設定でありながらいつの時代とも特定しないSFよりの物語。
オマル・エル・アッカドのデビュー作『アメリカン・ウォー 上下』は災厄まみれの、21世紀後半以降の北米を描いた小説。21世紀後半以降というところが気になる設定だ。
森谷明子の『花野に眠る 秋葉図書館の四季』は『れんげ野原のまんなかで』の続編。 秋葉図書館を舞台としたミステリだが、まさか続編が書かれるとは思わなかった。
思わなかったといえば、ジョー・ウォルトンが翻訳されるとは思わなかった。まあ、<ファージング>サーガが2010年、その次の『図書室の魔法』が2014年なので、このくらいの間隔で翻訳されるのであれば珍しいことではないけれども。
ハヤカワ文庫SFからはようやくコードウェイナー・スミスの全短編集最終巻が出る。ひょっとしたら出ないんじゃないかという気もしていたがよかった。
中公文庫からは小泉喜美子の短編集が復刊。小泉喜美子ファンとしては嬉しい限りです。
竹書房文庫からはいきなりの猫SFアンソロジーが出る。かつて扶桑社ミステリーからJ・ダン、G・ドゾワの編集による猫SFアンソロジー『魔法の猫』が出た事があるけれどもあれとは別物なのだろう。
門井慶喜の『注文の多い美術館』は美術探偵シリーズの第三弾。
塩田武士の『雪の香り』は感動必死の純愛ミステリーという謳い文句で、感動必死というのはゲンナリしてしまうのだが、塩田武士の小説は面白いので読むだろう。
文遊社からはジム・トンプスンの『天国の南』が出る。なんか凄いな。
続いて漫画。
秋田書店『イワとニキの新婚旅行』白井弓子
講談社『Pumpkin Scissors(21)』岩永亮太郎
集英社『そしてボクは外道マンになる(1)』平松伸二
集英社『ゴールデンカムイ(11)』野田サトル
小学館『銀の匙 Silver Spoon(14)』荒川弘
講談社『別式(2)』TAGRO
講談社『とんがり帽子のアトリエ(2)』白浜鴎
小学館『月曜日の友達(1)』阿部共実
集英社『ファイアパンチ(6)』藤本タツキ
秋田書店『AIの遺電子(7)』山田胡瓜
KADOKAWA『ダンジョン飯(5)』九井諒子
平松伸二よお前もかといいたくなるけれども、自伝的漫画、『そしてボクは外道マンになる(1)』が単行本化。『ドーベルマン刑事』とか『ブラック・エンジェルズ』を読んでいた身としては期待が大きい。
久しぶりに荒川弘の『銀の匙 Silver Spoon(14)』の新刊が出る。
久しぶりといえば、阿部共実の久しぶりの新作が今度は小学館から出る。小学館に移ってもおそらく今まで通りの阿部共実なのだろうなあ。
2017年07月20日 16:24
魔女の棲む町≫
カテゴリー │マグノリアブックス
人口三千人ほどの小さな町。その町には魔女の呪いがかけられていた。
そこに住んでいる人はその町から出ることができない。かりにその町から外に出たとしても、しばらくの間は大丈夫だが、数日後には死への欲望が高まり自殺してしまうのだ。この町で生まれた者、この町へ引っ越してきた者、すべてその町にとらわれてしまう。
ホラー小説なので普通ならば手に取るつもりはなかったのだが、作者がSF小説を書いていたことと、設定の部分がどこかジェローム・ビクスビイの「きょうも上天気」を彷彿させる内容だったことで思わず買ってしまった。
ジェローム・ビクスビイの「きょうも上天気」の場合は全知全能ともいえる能力を持った少年によって世界から隔離されてしまった小さな村を舞台に、全知全能の少年の怒りを買わないように、腫物でもさわるかのように少年に接するしかない村人たちの恐怖の物語だったが、この物語も同様で、ただし、あちらがある程度は少年とのコミュニケーションが可能であるのに対して、こちらの魔女はコミュニケーションが不可能である。目も口も堅く縫い取られており、両手も鎖でつながれているというのもその理由の一つだが、魔女自身が何も語ろうとしないのだ。
しかし、物語はそこから想像する方向へとは向かわない。
物語開始早々、主人公の息子が主人公に投げかける質問が物語全体を覆う。
自分の息子とスーダンのどこかの村人全員、どちらかが死ななければならないとしたらどちらを選ぶ?
主人公は息子が助かるほうを選ぶ。
続いて息子はこう質問する。
僕自身とこの町のほかの住人、どちらかに死んでもらわないといけないとしたらどちらを選ぶ?
主人公は答える前に質問する。
この町のほかの住人の中には妻やお前の弟もふくまれるのか。
イエス。
主人公は両方助けると答える。
ああ、そうである、家族が犠牲になるのであればこう答えるしかない。
物語が進むにつれて、魔女もかつて似たような選択をさせられたことがわかってくる。自分の息子が天然痘で亡くなってしまったために魔法でよみがえらせようとしたのだ。そしてよみがえった息子の姿を見たこの町の住人によって魔女として捉えられ、もう一人の娘を助けたければ息子を殺せと要求させられる。そして魔女は娘を助けるために息子を殺す。しかし、魔女自身も町の人によって処刑させられる。そこから魔女の呪いがこの町を支配する。
物語終盤、主人公は自分の息子か、町の住人かの選択をしてしまう。
町の住人の中には妻や次男も含まれる。
どちらも助けることはできやしない。
とても悲しい話である。
そこに住んでいる人はその町から出ることができない。かりにその町から外に出たとしても、しばらくの間は大丈夫だが、数日後には死への欲望が高まり自殺してしまうのだ。この町で生まれた者、この町へ引っ越してきた者、すべてその町にとらわれてしまう。
ホラー小説なので普通ならば手に取るつもりはなかったのだが、作者がSF小説を書いていたことと、設定の部分がどこかジェローム・ビクスビイの「きょうも上天気」を彷彿させる内容だったことで思わず買ってしまった。
ジェローム・ビクスビイの「きょうも上天気」の場合は全知全能ともいえる能力を持った少年によって世界から隔離されてしまった小さな村を舞台に、全知全能の少年の怒りを買わないように、腫物でもさわるかのように少年に接するしかない村人たちの恐怖の物語だったが、この物語も同様で、ただし、あちらがある程度は少年とのコミュニケーションが可能であるのに対して、こちらの魔女はコミュニケーションが不可能である。目も口も堅く縫い取られており、両手も鎖でつながれているというのもその理由の一つだが、魔女自身が何も語ろうとしないのだ。
しかし、物語はそこから想像する方向へとは向かわない。
物語開始早々、主人公の息子が主人公に投げかける質問が物語全体を覆う。
自分の息子とスーダンのどこかの村人全員、どちらかが死ななければならないとしたらどちらを選ぶ?
主人公は息子が助かるほうを選ぶ。
続いて息子はこう質問する。
僕自身とこの町のほかの住人、どちらかに死んでもらわないといけないとしたらどちらを選ぶ?
主人公は答える前に質問する。
この町のほかの住人の中には妻やお前の弟もふくまれるのか。
イエス。
主人公は両方助けると答える。
ああ、そうである、家族が犠牲になるのであればこう答えるしかない。
物語が進むにつれて、魔女もかつて似たような選択をさせられたことがわかってくる。自分の息子が天然痘で亡くなってしまったために魔法でよみがえらせようとしたのだ。そしてよみがえった息子の姿を見たこの町の住人によって魔女として捉えられ、もう一人の娘を助けたければ息子を殺せと要求させられる。そして魔女は娘を助けるために息子を殺す。しかし、魔女自身も町の人によって処刑させられる。そこから魔女の呪いがこの町を支配する。
物語終盤、主人公は自分の息子か、町の住人かの選択をしてしまう。
町の住人の中には妻や次男も含まれる。
どちらも助けることはできやしない。
とても悲しい話である。
2017年05月25日 16:13
始まりと終わり≫
カテゴリー │ホンの話
天久聖一の『書き出し小説』は古今東西の物語の書き出しの一行だけを集めた本である。
というのは嘘だ。
この本に集められたのはこの世に存在しない、ひょっとしたら存在するのかもしれないが、一般的には陽の目を見ることのない架空の物語の書き出しの一行である。
そんな、ありもしない物語の書き出しの一行だけを集めて、それでわざわざ一冊の本にするなんて意味のあること、いや価値のあるものなのだろうかと思った人は騙されたと思ってこの本を読んでみるといいと思う。
全てが琴線に触れる、とまではいかないが、この続きを読んでみたいと思わせる書き出しが沢山収録されている。
小説の書き出しで僕がすぐに思いつくのはウィリアム・アイリッシュの『幻の女』の書きだしだ。
である。
しかし、これは古い版のもので、途中で改訳されて
となった。
ウィリアム・アイリッシュが別名義のコーネル・ウールリッチ名義で書いた『喪服のランデブー』の書き出しもまた良い。
も好きな書き出しのひとつだ。
しかし、小説の場合は残念なことに、書き出しのすぐ後に、次の文章が続く。書き出しの一文だけ抜き出してこうして書いてみると、その素晴らしさがわかるけれども、すぐ後に次の文章が続くとその素晴らしさがすこしだけ霞んでしまうことが多い。
だからこそ、この本の存在価値というものはあるわけで、思う存分、書き出しの素晴らしさを味わうことが出来るのである。
一方で、最後の一行というのはあまり話題になることは少ない。
僕が知っている範囲だと、斎藤美奈子の『名作うしろ読み』という本が最後の一行を扱っている本なのだが、最後の一行というのはそれまでの物語を受け止める一行でもあるので、それだけを抜き出してもあまりおもしろくないのかもしれない。
ただ、横溝正史の「百日紅の下にて」という短編のラストの一文は印象に残っている。
というのは嘘だ。
この本に集められたのはこの世に存在しない、ひょっとしたら存在するのかもしれないが、一般的には陽の目を見ることのない架空の物語の書き出しの一行である。
そんな、ありもしない物語の書き出しの一行だけを集めて、それでわざわざ一冊の本にするなんて意味のあること、いや価値のあるものなのだろうかと思った人は騙されたと思ってこの本を読んでみるといいと思う。
全てが琴線に触れる、とまではいかないが、この続きを読んでみたいと思わせる書き出しが沢山収録されている。
小説の書き出しで僕がすぐに思いつくのはウィリアム・アイリッシュの『幻の女』の書きだしだ。
夜は若く、彼も若かった。が、夜の気分は甘いのに、彼の気分は苦かった。
である。
しかし、これは古い版のもので、途中で改訳されて
夜は若く、彼も若かったが、夜の気分は甘いのに、彼の気分は苦かった。
となった。
ウィリアム・アイリッシュが別名義のコーネル・ウールリッチ名義で書いた『喪服のランデブー』の書き出しもまた良い。
二人は毎晩八時に逢った。 雨の降る日も雪の日も、月の照る夜も照らぬ夜も
も好きな書き出しのひとつだ。
しかし、小説の場合は残念なことに、書き出しのすぐ後に、次の文章が続く。書き出しの一文だけ抜き出してこうして書いてみると、その素晴らしさがわかるけれども、すぐ後に次の文章が続くとその素晴らしさがすこしだけ霞んでしまうことが多い。
だからこそ、この本の存在価値というものはあるわけで、思う存分、書き出しの素晴らしさを味わうことが出来るのである。
一方で、最後の一行というのはあまり話題になることは少ない。
僕が知っている範囲だと、斎藤美奈子の『名作うしろ読み』という本が最後の一行を扱っている本なのだが、最後の一行というのはそれまでの物語を受け止める一行でもあるので、それだけを抜き出してもあまりおもしろくないのかもしれない。
ただ、横溝正史の「百日紅の下にて」という短編のラストの一文は印象に残っている。
蒼茫と暮れゆく廃墟のなかの急坂を、金田一耕助は雑嚢をゆすぶり、ゆすぶり、急ぎ足に下っていった。瀬戸内海の一孤島、獄門島へ急ぐために――。
2017年02月14日 15:56
5巻以内で完結する傑作漫画99冊+α 最後≫
その一
その二
その三の続きです。
その二
その三の続きです。
- 『かっこいいスキヤキ』泉昌之
一人の男が駅弁を食べるだけの話なのに、こんなにも面白いのは何故なんだろうか。
泉昌之は久住昌之と泉晴紀による合作時のペンネームで、久住昌之は原作担当で後に谷口ジローと組んで『孤独のグルメ』を発表している。グルメ漫画でありながら彼らの描く漫画は、何をどのような順番で食べるか、というところに焦点があたることが多い。先の駅弁を食べる話も、主人公が駅弁のご飯とおかずをどのような順番で食べるのかということにひたすらこだわる話だ。もちろん、まるまる一冊、そんな話で終わるわけではなく、この本は短篇集なのでそれ以外の話もある。タイトルが『かっこいいスキヤキ』なのでグルメ系の話が多いのかといえば意外なことにグルメ系の話はこの二編しかない。その他に、四畳半の安アパートに住むウルトラマンのシリーズがあるのだが、残念なことに後に円谷プロからの物言いがついて、最初の青林堂版にしか収録されていない。
- 『モジャ公』藤子・F・不二雄
五巻以内で完結している漫画を選ぶといっても、誰もが思いつくような漫画ばかりを選んでも面白くない。なので、漫画をあまり読まない人でも思い浮かべることのできるほど有名な漫画家の作品は選ばないようにしたけれども、この作品だけは別格としたい。藤子・F・不二雄の作品であれば短篇集の方が切れのある作品が多いけれども、一冊を選ぶとなると難しい。そうなると内容的にも文句なしでしかも一冊としてまとまっていて連作短編なので長編としても読むことができるこの作品がベストかなと思う。もっとも一冊にまとまっているといっても685ページもあるので質だけでなく量的にもずっしりくる。
物語はふとしたことから宇宙を旅することとなった地球人の少年、空夫と宇宙人モジャ公、そしてロボットのドンモのドタバタギャグの話。なのだが、それはあくまで最初のうち。中盤から後半にかけて、藤子・F・不二雄が自分の描きたいように描き始めたせいか、随所にSF的な仕掛けや設定が出始めてくる。ギャグ漫画だったはずのものがいつのまにかシリアスで、ダークな物語へと変貌しつつ、それでいてユーモアもギャグも残っている。藤子・F・不二雄の最良の部分がもっとも色濃く出た漫画だ。
ただ、残念なのは、この漫画が連載漫画でありながらも打ち切りだったことだ。物語は一応の終わりを迎えるのだが、それでも、藤子・F・不二雄が目指していたものはもう少し違ったものだろうと思う、
しかし、それは完結しながらも未完であるこの漫画の正しい終わり方だったのかもしれない。
- 『邪眼は月輪に飛ぶ』藤田和日郎
藤田和日郎はパワフルで面白い漫画を描く作家だ。しかもどの作品もきめ細かな伏線が貼られていて、一見すると無茶な設定であったとしても後の展開でその無茶な設定がしっかりと意味のあるものになっていて、しかもその後というのが単行本にして十巻以上も経ってからだったりする。そんなことを週刊連載で行っているのだからいったいどこまで最初から考えて物語を作っているのだろうか、感心する以前に恐れ入るばかりなのだが、残念なことに長い話が多い。連載の最初からつきあっているのであればまだしも、面白いよといわれて勧められた漫画が四〇巻以上もあったりすると躊躇してしまう。
しかし、そんな面白い漫画を描く人の作品に触れてみたいとなると短い話もたまには描いてくれよと注文を付けたくなるが、藤田和日郎の場合はそこも抜かりがないらしい。『邪眼は月輪に飛ぶ』は一巻で完結してそれでいて藤田和日郎の持ち味はしっかりと存在している。『黒博物館スプリンガルド』も捨てがたい。
- 『我が名は狼(1)』たがみよしひさ
- 『我が名は狼(2)』たがみよしひさ
たがみよしひさといえば、『軽井沢シンドローム』かたがみよしひさのミステリ好きな部分が全面に出た『NERVOUS BREAKDOWN』が有名。残念なことにどちらも5巻以上なので、5巻以内で完結する作品を選ぶとするとこの作品か『滅日』全2巻になるだろう。『PEPPER』も捨てがたいけれども、『滅日』にしろ『PEPPER』にしろ、たがみよしひさのシリアスな部分しか現れていない。
そこへいくと、『我が名は狼』の場合、場面の切り替えにセリフを重ねあわせる、たがみ節こそないが、コミカルな場面では3頭身、シリアスな場面では8頭身で描かれる作風はすでに完成された物となっている。
長野県にあるペンションたかなしに、オーナーの親友の息子、犬神内記が訪れるところから物語は始まる。基本的に一話完結の物語で、毎回毎回、ペンションたかなしに宿泊しにきた女性が主人公と関わることによって物語が展開していく。しかし、犬神内記は一応の主人公でありながら、本当の主人公はペンションたかなしに訪れた宿泊客の女性の方なのだ。どの女性もなんらかの悩みを抱えており、犬神内記と関わりあうことによって少しだけ救われる。そしてそれぞれの物語も、幽霊奇譚風だったり、スキー場に現れる雪女の謎の物語だったり、殺人事件の謎を解く話だったりと、女性の悲哀を中心とした愛憎劇でありながらその味付けは多種多彩だ。
描かれた時代が時代だけに古臭く感じる部分もあるかもしれないが、読み進めていくうちにたがみよしひさの世界にどっぷりと浸かる心地よさを感じるはず。
オリジナルは全3巻だが後に2冊にまとめられた文庫がでている。
- 『カラメルキッチュ遊撃隊(1)』大石まさる
- 『カラメルキッチュ遊撃隊(2)』大石まさる
- 『カラメルキッチュ遊撃隊(3)』大石まさる
なかなか漫画を描いてくれない鶴田謙二の隙間を保管してくれるのが大石まさるだ。
そのことを本人が意識しているのかどうかわわからないけれども、<水惑星年代記>シリーズは絵柄まで鶴田謙二ふうの絵柄で、しかも7冊出してくれたので堪能することができた。
それ以降はおそらく意図的に絵柄も作風も変化させようとしているようで、鶴田謙二から脱却した大石まさるの変化は今のところ試行錯誤っぽい部分もある。
主人公が大人の女性である『ライプニッツ』も悪くないが、ここはあえてジュブナイルSFである『カラメルキッチュ遊撃隊』全3巻を選んでみた。
ある日突然、青い月が現れた時、地球上の都市が地表からえぐり取られるような形で消滅した。物語はそれから十数年後の話、都市部以外に住む人々達は少しずつ文明を復興させていたのだが、この「大消滅」以降、あちらこちらでイホージンと呼ばれる謎の生命体達があちらこちらに出没するようになる。「大消滅」とイホージンの謎を縦糸に繰り広げられる物語は、三人の少女たちの夏休みを中心としたほのぼのとした物語で、シリアスな基本設定とは裏腹に非常に良質なジュブナイル物語となっている。
主人公たちが「大消滅」の時点ではまだ赤ん坊で、「大消滅」以降の世界しか知らないというところが一つのポイントで、大人と子供との間における世代間の格差が物語の主題の一つとなっている。
最終巻では矢継ぎ早に話が進み、もう少しじっくり描いてもよかったんじゃないかとも思わせるのだが、その一方で、一気に物語を畳み込むこのスピード感と、あちらこちらに散りばめられた情報の密度の高さは、むしろやみくもに丁寧に描けばいいものではないという良い見本でもある。
- 『春風のスネグラチカ』沙村広明
現在のロシアという国が、かつてはソビエトという名前で呼ばれていたことを知らない世代も多くなってきた。さらにはそのソビエトでさえその前はロシアと呼ばれていて、ロシアという国がソビエトになってそしてまたロシアになった時、ロシア人はソビエトという国があったことを無かったことにしたかったのだろうかと思った。
それはさておき、この物語はかつてのロシア、ロシア帝国と呼ばれた時代から革命をへてソビエトとなった時代の物語。最近の沙村広明にしてはめずらしく直球どまんなかのシリアスな物語だ。
両足が義足の車いすに乗った少女と彼女に付き添う片目の青年。二人の素性はまったく語られず、謎のままに物語は進む。あまり内容について触れてしまうと二人の正体がわかった時の驚きが失われてしまうので、これ以上は書かないが、二人の正体が判明したときに判る歴史の隙間の部分をうまく埋めたミステリとして堪能することができると同時に、沙村広明の持ち味の一つである、サディスティックで猟奇的な、いってしまえば作者の趣味がうまく物語とミックスされた作品でもある。
- 『Pの悲劇』高橋留美子
高橋留美子も藤田和日郎と同じく、とにかく長いお話を描く。どこまでそのことを自覚しているのかわからないけれども、これだけの長いキャリアのなかで、いまだに衰えを見せないのも凄い。しかし、高橋留美子の場合は時々短編を描いている。主に大人向けの話なのだが、高橋留美子は短編を描かせてもうまい。長い連載の合間に、よくもまあこんなに質の高い短編を描くことができるものだと感心するしかない。
表題作はペット禁止の団地でお得意先のお客さんが飼っているペットのペンギンを一時的に預からなくてはいけなくなったとある家族の話。短編ながらも4つの章に分けられ、それぞれ「P」で始まる単語の題名がつけられているという凝りよう。団地の中でも動物をこっそりと飼っている人もいて、一方で規則を厳守する運動をしている人達もいる。双方の対立する中、主人公一家は預かっているペンギンの秘匿に苦労をするのだが、登場人物の一人が言う「動物が好きな人は善人で、嫌いな人は悪人なのか」という言葉は考えさせられる。
この短篇集の中で唯一、コメディでないのが「鉢の中」という短編。嫁と姑の確執の話で、お嫁さんが義理の母をいじめていたという噂が流れる中、真相は全く異なっていたという、これまたタイトルが意味深なタイトルで、本当のことが明らかになっても決して救われるわけではなく、それでも真実を受け入れなくてはならないという辛い話なのだが、こういう話が一本あるだけで、短篇集全体がキリッと締まって良い本となる。
- 『LOVE SYNC DREAM(1)』ジーディー・モルヴァン(作)、藤原カムイ(絵)
- 『LOVE SYNC DREAM(2)』ジーディー・モルヴァン(作)、藤原カムイ(絵)
ジーディー・モルヴァンはフランスの漫画原作者。『LOVE SYNC DREAM』の他に寺田亨の『Le Petit Monde―プチ・モンド』の原作も手がけている。
その他に、ファン・ジャーウェイが絵を手掛けた『ZAYA』の原作も手がけているが、日本では残念なことに1巻しか翻訳されていない。
ニコラ・ド・クレシーの『プロレス狂想曲』はバンド・デシネの漫画家が日本の漫画雑誌に連載をするという形であったが、この『LOVE SYNC DREAM』はフランス漫画の原作者によるシナリオを日本人の漫画家、藤原カムイが漫画に仕立てあげた、いわゆるフランスと日本のコラボレーション作品。
しかし、誰と組もうが、何を描こうが、藤原カムイは藤原カムイで、おしゃれでポップでキュートでそれでいて様々な実験的な表現があったり、あちらこちらにサブカルネタが織り込まれている。どこまでが藤原カムイの部分でどこがジーディー・モルヴァンの部分なのか判別がつかないほど見事に融合している。
- 『海辺へ行く道 夏』三好銀
- 『海辺へ行く道 冬』三好銀
- 『海辺へ行く道 そしてまた、夏』三好銀
もの凄く静かで、何かとてつもない恐ろしいことが起こっているような予兆を感じさせながらも、その恐ろしさはあくまで断片的であり、明確な形として物語の表面には現れない。
そこに描かれるのはたわいもない日常であり、夏休みの自由研究をする高校生の話のだったり、落し物を引き取りに病院まで行って帰るだけの話だったり、主婦に包丁を売りつける詐欺師の話だったり、まあ最後の話は日常生活の話とはちょっと違うかも知れないが、日常生活からかけ離れた特別な事件が起こるわけではない。
まどの一哉の『洞窟ゲーム』にも似た雰囲気があるのだが、まどの一哉のように狂気が見えてこない。何かが変で、それをさほど変と思わない登場人物も変で、言い換えれば、地球人とは思考回路の異なる異星人が地球人の扮装をして地球人っぽい生活をしようとしている風景を覗かせられているといった方がいいだろうか。
この漫画を読む読者は彼らの生活を無理矢理見せられているのだ。
見せられるといえば、三好銀が見せる構図も不安感をかき立てさせられる。
背景にしろ、構図にしろ、どこか変なのだ。
パースもろくに取れない下手な絵だといってしまえば簡単なのだが、下手だったらこうも変に描くことなどできやしないだろう。意図的に不安感を高めさせようとしているとしかいいようがない。
作者の三好銀は2016年8月31日に逝去した
唯一無二ともいえる独特な世界をもう見ることができないのは悲しい。
- 『棒がいっぽん』高野文子
高野文子だったらそもそも作品数が少ないのでどれを選んでも構わない気もする。もっとも現時点での最新作『ドミトリーともきんす』は初めての高野文子としてはちょっとハードルが高い気もするが。
というわけで全作品を挙げてもよかったし、『黄色い本』を選ぶのが妥当なところなんだろうけれども、あえてこの一冊を選んだ。決め手は「奥村さんのお茄子」が収録されているからで、高野文子にしか描きようのないSFでもあるからだ。
1968年6月6日の昼飯に奥村さんが茄子を食べたかどうかというのが物語の焦点にあたる。1986年というのは物語の中では25年も昔のことである。そんな昔のしかもそれほど特別ではない日の昼飯のことなど覚えているはずもなく、そこからいろいろなことが起こるのだけれども、すんなりと読めばそれなりに面白く読むことができる話でありながら、いろいろと考えだすと様々な解釈をすることができ、一筋縄ではいかない話なのだ。
- 『バットマン/ヘルボーイ/スターマン』マイク・ミニョーラ
アメコミというと、いわゆるバタ臭い絵というイメージを持っている人が多いと思う。僕もそんな印象を持ち続けていたのだが、そんなアメコミのイメージを一蹴してくれたのがマイク・ミニョーラだ。彼の描く絵はそれまでのバタ臭い絵とは一線を画して、日本人にも受けやすい絵柄だと思う。影のコントラストのメリハリの効いた切り絵的な趣もある絵だ。そんな彼の作品から一冊を選んでみたいのだが、代表作である『ヘルボーイ』は五冊以上出ているし、後半の作品ではミニョーラは作画をしていない。困ったなあと思っていたのだが、しかし大丈夫。この作品があった。マイク・ミニョーラが生み出したキャラクター、ヘルボーイの魅力を味わう事ができるうえに、さらにクロスオーバー作品なので、タイトルに書かれているようにバットマンとスターマンもミニョーラの手によって描かれていて一粒で二度美味しい作品だ。もっとも、スターマンは日本ではあまり知られていない存在なのだが、知らなくてもそれほど支障はない。
- 『三文未来の家庭訪問』庄司創
『アフター0』の岡崎二郎のようなタイプの作風。
短篇集なのだが、わずか三編しか収録されていない。この本の最後に収録された「辺獄にて」はシンプルな構造の物語なのだが、それ以外の二作品は、そんな部分にまでアイデアを注ぎ込むかと言いたくなるような密度の濃さで、特に表題作は表層レベルにおいてはボーイ・ミーツ・ガールという物語でありながらも、そこに男性という性の多様性のありかたというSF的なアイデアと概念の構築と、そこから発生する社会の変貌というものを描きながらも同時に、そこから発生する社会とは別の社会様式というものを設定しておいて、二つの、実際にはもう一つの社会が存在するのだが、それらの社会を混ぜあわせたかたちで主人公の恋の物語を描いている。
およそSF漫画らしくない絵柄なので画力でもってSFの世界を魅せるタイプではなく、思弁の畳み掛けでSFの持つ不思議さを魅せるタイプなので、一度味わってしまえば面白さがわかるが、漫画としては損をしている部分もある。
- 『海帰線』今敏
46歳で急逝してしまった今敏の一冊。もっとも今敏の場合、漫画家としてよりもアニメーション監督としてのほうが有名だろう。
『PERFECT BLUE』『千年女優』『東京ゴッドファーザーズ』そして『パプリカ』。
アニメーションに携わる前に描かれた作品なので後年の作品と比べれば物足りない部分もあるかもしれない。しかし、前半の、はっきりいってしまえば地味な、それでいて丁寧に描かれていく登場人物たちの心理描写が後半になって一気に一つにまとまって収束していくさまは圧巻だ。郷愁を感じさせる世界といい、大友克洋を彷彿させる緻密に描かれた絵といい、作者がアニメの世界に行ってしまったことを残念に思ってしまうくらいなのだが、アニメの方を見れば見たで今度は急逝してしまったことを残念に思ってしまう。
しかし、それでも作品が残されていてそしていつでもそれに触れることができるということはそれだけで幸せなのかもしれない。
- 『サルタン防衛隊』大友克洋・高千穂遙(作)、高寺彰彦(絵)
2015年、大友克洋は第42回アングレーム国際漫画フェスティバルで日本人として初めて最優秀賞を受賞した。そのときの公式サイトで背景画像として使われていた大友克洋の作品の絵のなかにフランス語版の『サルタン防衛隊』の表紙絵を見つけたとき、おもわずにんまりとしてしまった。『サルタン防衛隊』は大友克洋は原作として関わっただけで、作画のほうは高寺彰彦だったからで、高寺彰彦のファンとしてうれしかったのだ。もちろんこの背景画像の中には同じく原作として関わった『沙流羅』の含まれていたので『サルタン防衛隊』だけが特別扱いだったというわけではない。
訪日中の中東の首長(サルタン)を時期首長の座を狙っている副首長が暗殺を企て、日本にやってくる。その情報を入手した日本側は、副首長が親日派であることと今後の外交的優位を得るために、訪日中の首長の警護に選んだ人物は警視庁のエリートではなく、暗殺を阻止できそうもない問題児ばかりだった。エリートで構成された暗殺部隊と落ちこぼれ問題児たちの戦いという構図は定番ながら燃えるものがある。僕はこの手の物語が大好きだ。はたして警察の落ちこぼれたちはサルタンを守り切ることができるのだろうか。
- 『時の鳥を求めて』セルジュ・ル・タンドル(作)、レジス・ロワゼル(絵)
ここまでストレートなヒロイックファンタジーというのは珍しい気もする。
220ページ弱とページ数は少ない。一般的にファンタジー物語というとやたらと長大な物語というイメージもあるし、日本の漫画の一般的なページ数と比較してみてもやはり少ない。しかし、いざ読み始めるとこれが長く感じられる。一コマ一コマの絵の魅力に魅了され、ページをめくる手が進まないのだ。多分これは日本のマンガが一瞬を切り取って一コマにしているのに対して、一コマに様々な情報を詰め込み、一コマの中で時間の流れの変化さえも描いているせいでもあると思う。だから、全体のページ数は少なくてもそこに詰め込まれた情報量は決して少なくはない。
その一方で、絵の魅力もさておき物語の方も単純な物語ではなく、多少説明不足と思う部分もありながらもそこは想像で補うとして、ストレートなヒロイックファンタジーでありながらも、引退した老騎士と彼の娘かもしれないヒロインの世界を救う旅の物語は、次第に老騎士自身の物語と重ね合わさり、そして最後に一つに重なって行くという凝った構成になっている。
- 『I KILL GIANTS』ジョー・ケリー(作)、ケン・ニイムラ(絵)
外務省が主催する第5回国際漫画賞で最優秀賞を受賞した作品。
頭にうさぎの耳が付いている少女が主人公で、しかも題名が『I KILL GIANTS』と巨人を倒す話しである。だからてっきりファンタジーだと思ってしまうのは間違いで、そこで語られる物語は現実的でちょっと戸惑ってしまくらいにかなり深刻な話だ。
深刻だといってもここで描かれる物語はそれほど特異でもなく今までなかったような新しい物語でもないのだが、主人公がTVゲームではなく、テーブルトークRPGで遊んでいるところや、ある重要な言葉が吹き出しの中で黒く塗りつぶされているという表現方法、そして主人公がカウンセリングを受けていることなどなど、日本とアメリカとの文化的な違いが、ここまで物語として異なるアプローチの仕方になるということは興味深い事柄でもある。いうなれば主人公が抱える問題に対する作者のアプローチの仕方が極めて西洋的であり、論理的なのだ。日本でもアメリカでも多感な時期の子どもたちが抱える悩みに変わりはないけれども、それを漫画で表現するとこうも違う形で描かれるというのは興味深いことだ。
- 『のらずにいられないっ!』寺田克也
5巻以内で完結する漫画を選ぶ際に、出来る限りいろいろなジャンルの漫画を選ぶようにしてみたのだが、選ぶのが難しいジャンルが二つだけあった。
一つはスポーツ漫画。
もう一つはレース漫画だ。
どちらも傑作と言われる漫画は多い。しかし、どちらも傑作であればあるほど、長いのだ。
スポーツもレースも競技を描く必要がある。物語の面白さを描く上で、その競技を描く必要があるので長くならざるをえないのだと思う。
で、さんざん悩んだ末に、スポーツ漫画ではバスティアン・ヴィヴェス『ポリーナ』を選んだ。競技を描かずにバレリーナの人生の方を描いた漫画だ。
そして、レース漫画はちょっと苦しいけれども、自動車を描いたこの漫画で代用することにした。
いつかCaterham SEVENという車に乗りたいと思っていた。もっとも、今でも乗ってみたいという気持ちは少し残っているけれど、この車にのるということは道楽であり、この手の道楽をするにはいろいろと気合を入れなければ楽しむことができそうもないので、今では妄想で楽しむ程度にしている。多分、実際に手に入れたとしても根が不精なのでこまめなメンテナンスとか無理だろうからだ。
しかしこういった、いっぷう変わった車というのは昔も今も好きで、だからこの本も読んでいて楽しい。
とくに、寺田克也の手によって描かれた車たちは、必ずしも写実的ではないのにリアルで、なまめかしくて、さらには愛嬌もあって、こんな車だったら不便なところがあったとしても、はたまたやたらと壊れてしまったりしても、この車にのるということを楽しむ事ができるんじゃないか。そんなふうに、あやうく騙されそうになってしまうくらいになるほど魅力的に描かてれいる。
実際にのることができなくってもこの本をながめているだけで十分に楽しい。
- 『漫画家超残酷物語 青春増補版』唐沢なをき
最後は、こんなにも楽しませてくれる漫画を描いた作者のほうに目を向けてみよう。
唐沢なをきの『漫画家超残酷物語 青春増補版』はタイトルから想像できるように永島慎二の『漫画家残酷物語』全3巻のパロディだ。
だったら永島慎二の『漫画家残酷物語』の方を選んだほうが良かったんじゃないかという意見も出てきそうなんだけれども、さすがに『漫画家残酷物語』は今となっては古びてしまっている。もちろん作品そのものの価値は揺るぎないものだけれども、ここで描かれている漫画家たちは1960年代に生きた漫画家たちで、漫画家に目を向けるという意味だと少し辛い気がする。だったら両方選んでしまえばいいじゃないかという考えもあったが『漫画家残酷物語』は全三巻なので、これを入れると他の作品をはずさなくてはいけないので敢えてここでは現代風にアレンジしたパロディである『漫画家超残酷物語 青春増補版』を選んだ。『漫画家超残酷物語 青春増補版』の最初の話は「サムソン」という題名だが、この作品は『漫画家残酷物語』の中にある「うすのろ」のパロディだ。名作と呼ばれる作品のパロディに挑戦し、なおかつ元ネタを知らなくても十分におもしろい作品に仕上がっている。そしてなおかつ、ギャグ漫画でありながら漫画家というものの業の深さと、オリジナルである『漫画家残酷物語』が描いている若き漫画家たちの苦悩や夢や希望、そして挫折もあますところなくすくい上げている。
さて、これで以上99冊の漫画について触れてみた。
もちろん、これ以外にも5巻以内で完結する面白い漫画はある。
できることならば、100冊目は永島慎二の『漫画家残酷物語』を選んで欲しい。
時代はまた過去にさかのぼり、そして今度はあなたの99冊を見つけてもらいたい。
2017年01月16日 16:18
2016年の回顧≫
カテゴリー │ホンの話
小説と比べて漫画のほうは電子書籍化される率が高いうえに、蔵書スペースというものを考えなくてもすむので、ついつい漫画を読む比率が高くなってしまう。
去年無事完結した漫画で面白かったものは、
『WOMBS』全5巻 白井 弓子
『変身!』全3巻 横山 旬
『僕だけがいない街』全8巻 三部 けい
『橙は、半透明に二度寝する』全2巻 阿部洋一
『WOMBS』は途中から連載ではなく描き下ろしという形になったけれども、掲載誌が休刊という状態になってしまい、それにともなって掲載誌の名前を冠したレーベルも終了せざるをえなくなり、結果、描き下ろし作品とはいえども、残り1巻しか出すことができなくなってしまったという残念な結果になってしまった。おそらくは完結までに2巻くらいは必要としたかも知れない物語を1巻で収めなければいけなくなったためにか終盤は畳み掛けるようなスピードで物語りが収束していくのだが、ありえたかもしれない本来の物語も読みたかったというのはわがままだろう。
同様に『変身!』もそれまでののんびりとした展開からすれば少し違和感を感じるくらいのスピードで物語が収束していった。幼少期からの成長物語という体裁でありながら、最後まであまり成長することのなかった主人公の物語はもう少し先まで読みたかったという気持ちもあるが、成長しない主人公なのでこれはこれでコンパクトにまとまったというべきなのだろう。
それに比べると『僕だけがいない街』は十分な長さで、満足した話だった。
『橙は、半透明に二度寝する』は長編ではないので本当にこれで完結したのかと疑問に思う部分もあるけれども、最終話は最初の第一話につながる円環構造となっているので、これで完結したのだろう。
その他で面白かったのは次の2冊
『兎が二匹』全2巻 山うた
『カナリアたちの舟』高松 美咲
『兎が二匹』はアンハッピーエンドから始まる物語。ハッピーエンドにはならない物語がどのような結末を迎えるのかといえばアンハッピーエンドにしかならないはずなのだが、隙間を縫ってここしかないという地点に着地する。
『カナリアたちの舟』も同様にアンハッピーエンドにしかならないような悲しい物語。
完結していないけれども面白い漫画に関してはここでは触れないことにする。
2016年はあまりSFを読まなかった。いや2015年もあまり読んでいなかった気もする。買っていないというわけではなくって積読のままなので、周回遅れ的な感じで読んでいくことになるだろう。
『宇宙探偵マグナス・リドルフ』ジャック・ヴァンス
『天界の眼 切れ者キューゲルの冒険』ジャック・ヴァンス
『スキャナーに生きがいはない 人類補完機構全短篇1』コードウェイナー・スミス
『アルファ・ラルファ大通り 人類補完機構全短篇2』コードウェイナー・スミス
『現代SF観光局』大森望
『ミルキーピア物語』東野司
国書刊行会のことなので出すと発表しても実際に出るのはだいぶ先だと思っていたジャック・ヴァンスの作品を集めた<ジャック・ヴァンス・トレジャリー>の一冊目と二冊目がまたたくまに出た。全3巻のこのシリーズも残すところ最後の1冊となったのだが、ヴァンスの未訳作品はまだまだたくさんあるのでこの勢いにのせてどんどん翻訳されるとうれしい。
ジャック・ヴァンスと同じく偏愛している作家、コードウェイナー・スミスの<人類補完機構>シリーズの全短編を三冊にまとめたシリーズのうち2冊が出た。刊行ペースからみて、2016年内には3冊目が出ると思ったらそうでもなく年を越してしまった。
『現代SF観光局』はSFマガジンに連載していたコラムをまとめたもの。こうして一冊にまとまってみると実に密度が高く、読んでいる時間が楽しかった一冊。
紙の本ではなく電子書籍の方ではあるけれども<ミルキーピア物語>シリーズが全巻復刊した。基本的には文庫で出ていたこのシリーズも最終作とその一つ前の作品はSFマガジン連載とその増刊号という扱いで出たために、当時の僕はいつか文庫化されるだろうと待ち続けてそしてそれっきりとなってしまっていた。
文庫化されなかった理由とかこのシリーズにまつわる話は『ミルキーピア物語(9) 京美・誕生 小さなイヤリング』にミルキーピア物語顛末記として書かれている。
広義のミステリとして、面白かったのは以下の五冊
『オータム・タイガー』ボブ・ラングレー
『ゲルマニア』ハラルト・ギルバース
『拾った女』チャールズ・ウィルフォード
『殊能将之未発表短篇集』殊能将之
『血の極点』ジェイムズ・トンプソン
復刊してくれたおかげで読むことのできたボブ・ラングレーの『オータム・タイガー』は名作と言われるだけあって面白かった。冒険小説の部類だけれども、面白い冒険小説を読むと他の冒険小説も読みたくなる。
『ゲルマニア』は翻訳されたのは2015年で一昨年なんだけれども、その時からちょっと気になっていたが、分厚かったので先延ばしにしていた作品。その後続編が翻訳されたので、思い切って読んでみた。謎解きとしてはそれほど驚く内容ではないけれども、敗戦間近のベルリンを舞台に、ユダヤ人の元刑事が連続殺人事件を追うという設定勝ちの話で、これで面白くならない方がおかしかった。
チャールズ・ウィルフォードの『拾った女』は暗黒小説。主人公たちの行動からして既に破滅に向かって一直線でありながら、物語は一直線ではない曲者。
殊能将之が亡くなって3年。最後の長編が2004年で、その後は2009年に短編ひとつだけ発表しただけだったので、未発表短編があったとは思いもよらなかった。しかし、小説の数はともかくとして文章量は膨大な人だったと思う。
殊能将之と同じく突然の訃報に驚いたジェイムズ・トンプソンの遺作『血の極点』も無事翻訳された。主人公たちの物語はまだまだ続くのだろうけれども、この話で終わってもそれほど違和感は無い。
SFとミステリ以外で面白かったものは次の8冊
『なんらかの事情』岸本佐知子
『スタッキング可能』松田青子
『俺はNOSAKAだ』野坂昭如
『ピダハン―― 「言語本能」を超える文化と世界観』ダニエル・L・エヴェレット
『戦地の図書館 海を越えた一億四千万冊』モリー・グプティル・マニング
『明日、機械がヒトになる ルポ最新科学』海猫沢めろん
『この恋と、その未来。5 ―二年目 秋冬―』森橋 ビンゴ
『この恋と、その未来。6 ―三年目 そして―』森橋 ビンゴ
やたらと面白いエッセイを書く岸本佐知子の『なんらかの事情』は文庫化にあたり未収録分を少し増量。
こんな文章を書かれたら自分がこうしてブログで駄文なんて書いているのが恥ずかしくなるくらいに素晴らしかったのが『スタッキング可能』
『俺はNOSAKAだ』は「骨餓身峠死人葛」が収録されていたので購入。
野坂昭如の作品はほとんどが絶版になって久しいが、著者が亡くなったことを機に入手困難だった作品がまたこうして読めることとなった。「骨餓身峠死人葛」以外にも「乱離骨灰鬼胎草」も収録されていて堪能することができた。
太郎は生きていると次郎は考えていた。
というような再帰的な文章を作ることのできない言語、ピダハン語とその言語を使うピダハンの人々についてのノンフィクション。
再帰がないだけではなく、家族関係を表す言葉や数を表す言葉などがなく、神話にあたる物語も持ち得ていない種族ピダハンの文化というのは興味深いうえにいろいろと考えさせられる。言語的に特異なピダハン語でコミュニケーションを取ることができているということを考えると、人工知能における言語のあり方の可能性というものにも一考の価値があるのではないだろうか。
第二次世界大戦中、アメリカはドイツと武力での戦いをしていたが同時に書物でもっても戦いを挑んでいたというのが『戦地の図書館 海を越えた一億四千万冊』。
本の力いや、物語の力の大きさをまざまざと見せつけてくれる。
小説ばかりではなくノンフィクションも書いていたのに驚いたのが海猫沢めろん『明日、機械がヒトになる ルポ最新科学』。
さまざまな技術の最前線の人たちにインタビューを行い、そして機械と人とのつながり、それは単純に人が機械をどのように扱うべきなのかというような問題ではなく、機械を人に近づけていくという世界と、人は機械に置き換えるあるいは、人と機械との違いといった哲学的な問題を垣間見せてくれた。
『この恋と、その未来。』は5巻で打ち切りになるはずだったのが、とにかく最終巻まで出せてよかったよ。内容はといえばライトノベルとして文句なしで、ライトノベルとして出すことができたということにも意義があると思う。
去年無事完結した漫画で面白かったものは、
『WOMBS』全5巻 白井 弓子
『変身!』全3巻 横山 旬
『僕だけがいない街』全8巻 三部 けい
『橙は、半透明に二度寝する』全2巻 阿部洋一
『WOMBS』は途中から連載ではなく描き下ろしという形になったけれども、掲載誌が休刊という状態になってしまい、それにともなって掲載誌の名前を冠したレーベルも終了せざるをえなくなり、結果、描き下ろし作品とはいえども、残り1巻しか出すことができなくなってしまったという残念な結果になってしまった。おそらくは完結までに2巻くらいは必要としたかも知れない物語を1巻で収めなければいけなくなったためにか終盤は畳み掛けるようなスピードで物語りが収束していくのだが、ありえたかもしれない本来の物語も読みたかったというのはわがままだろう。
同様に『変身!』もそれまでののんびりとした展開からすれば少し違和感を感じるくらいのスピードで物語が収束していった。幼少期からの成長物語という体裁でありながら、最後まであまり成長することのなかった主人公の物語はもう少し先まで読みたかったという気持ちもあるが、成長しない主人公なのでこれはこれでコンパクトにまとまったというべきなのだろう。
それに比べると『僕だけがいない街』は十分な長さで、満足した話だった。
『橙は、半透明に二度寝する』は長編ではないので本当にこれで完結したのかと疑問に思う部分もあるけれども、最終話は最初の第一話につながる円環構造となっているので、これで完結したのだろう。
その他で面白かったのは次の2冊
『兎が二匹』全2巻 山うた
『カナリアたちの舟』高松 美咲
『兎が二匹』はアンハッピーエンドから始まる物語。ハッピーエンドにはならない物語がどのような結末を迎えるのかといえばアンハッピーエンドにしかならないはずなのだが、隙間を縫ってここしかないという地点に着地する。
『カナリアたちの舟』も同様にアンハッピーエンドにしかならないような悲しい物語。
完結していないけれども面白い漫画に関してはここでは触れないことにする。
2016年はあまりSFを読まなかった。いや2015年もあまり読んでいなかった気もする。買っていないというわけではなくって積読のままなので、周回遅れ的な感じで読んでいくことになるだろう。
『宇宙探偵マグナス・リドルフ』ジャック・ヴァンス
『天界の眼 切れ者キューゲルの冒険』ジャック・ヴァンス
『スキャナーに生きがいはない 人類補完機構全短篇1』コードウェイナー・スミス
『アルファ・ラルファ大通り 人類補完機構全短篇2』コードウェイナー・スミス
『現代SF観光局』大森望
『ミルキーピア物語』東野司
国書刊行会のことなので出すと発表しても実際に出るのはだいぶ先だと思っていたジャック・ヴァンスの作品を集めた<ジャック・ヴァンス・トレジャリー>の一冊目と二冊目がまたたくまに出た。全3巻のこのシリーズも残すところ最後の1冊となったのだが、ヴァンスの未訳作品はまだまだたくさんあるのでこの勢いにのせてどんどん翻訳されるとうれしい。
ジャック・ヴァンスと同じく偏愛している作家、コードウェイナー・スミスの<人類補完機構>シリーズの全短編を三冊にまとめたシリーズのうち2冊が出た。刊行ペースからみて、2016年内には3冊目が出ると思ったらそうでもなく年を越してしまった。
『現代SF観光局』はSFマガジンに連載していたコラムをまとめたもの。こうして一冊にまとまってみると実に密度が高く、読んでいる時間が楽しかった一冊。
紙の本ではなく電子書籍の方ではあるけれども<ミルキーピア物語>シリーズが全巻復刊した。基本的には文庫で出ていたこのシリーズも最終作とその一つ前の作品はSFマガジン連載とその増刊号という扱いで出たために、当時の僕はいつか文庫化されるだろうと待ち続けてそしてそれっきりとなってしまっていた。
文庫化されなかった理由とかこのシリーズにまつわる話は『ミルキーピア物語(9) 京美・誕生 小さなイヤリング』にミルキーピア物語顛末記として書かれている。
広義のミステリとして、面白かったのは以下の五冊
『オータム・タイガー』ボブ・ラングレー
『ゲルマニア』ハラルト・ギルバース
『拾った女』チャールズ・ウィルフォード
『殊能将之未発表短篇集』殊能将之
『血の極点』ジェイムズ・トンプソン
復刊してくれたおかげで読むことのできたボブ・ラングレーの『オータム・タイガー』は名作と言われるだけあって面白かった。冒険小説の部類だけれども、面白い冒険小説を読むと他の冒険小説も読みたくなる。
『ゲルマニア』は翻訳されたのは2015年で一昨年なんだけれども、その時からちょっと気になっていたが、分厚かったので先延ばしにしていた作品。その後続編が翻訳されたので、思い切って読んでみた。謎解きとしてはそれほど驚く内容ではないけれども、敗戦間近のベルリンを舞台に、ユダヤ人の元刑事が連続殺人事件を追うという設定勝ちの話で、これで面白くならない方がおかしかった。
チャールズ・ウィルフォードの『拾った女』は暗黒小説。主人公たちの行動からして既に破滅に向かって一直線でありながら、物語は一直線ではない曲者。
殊能将之が亡くなって3年。最後の長編が2004年で、その後は2009年に短編ひとつだけ発表しただけだったので、未発表短編があったとは思いもよらなかった。しかし、小説の数はともかくとして文章量は膨大な人だったと思う。
殊能将之と同じく突然の訃報に驚いたジェイムズ・トンプソンの遺作『血の極点』も無事翻訳された。主人公たちの物語はまだまだ続くのだろうけれども、この話で終わってもそれほど違和感は無い。
SFとミステリ以外で面白かったものは次の8冊
『なんらかの事情』岸本佐知子
『スタッキング可能』松田青子
『俺はNOSAKAだ』野坂昭如
『ピダハン―― 「言語本能」を超える文化と世界観』ダニエル・L・エヴェレット
『戦地の図書館 海を越えた一億四千万冊』モリー・グプティル・マニング
『明日、機械がヒトになる ルポ最新科学』海猫沢めろん
『この恋と、その未来。5 ―二年目 秋冬―』森橋 ビンゴ
『この恋と、その未来。6 ―三年目 そして―』森橋 ビンゴ
やたらと面白いエッセイを書く岸本佐知子の『なんらかの事情』は文庫化にあたり未収録分を少し増量。
こんな文章を書かれたら自分がこうしてブログで駄文なんて書いているのが恥ずかしくなるくらいに素晴らしかったのが『スタッキング可能』
『俺はNOSAKAだ』は「骨餓身峠死人葛」が収録されていたので購入。
野坂昭如の作品はほとんどが絶版になって久しいが、著者が亡くなったことを機に入手困難だった作品がまたこうして読めることとなった。「骨餓身峠死人葛」以外にも「乱離骨灰鬼胎草」も収録されていて堪能することができた。
太郎は生きていると次郎は考えていた。
というような再帰的な文章を作ることのできない言語、ピダハン語とその言語を使うピダハンの人々についてのノンフィクション。
再帰がないだけではなく、家族関係を表す言葉や数を表す言葉などがなく、神話にあたる物語も持ち得ていない種族ピダハンの文化というのは興味深いうえにいろいろと考えさせられる。言語的に特異なピダハン語でコミュニケーションを取ることができているということを考えると、人工知能における言語のあり方の可能性というものにも一考の価値があるのではないだろうか。
第二次世界大戦中、アメリカはドイツと武力での戦いをしていたが同時に書物でもっても戦いを挑んでいたというのが『戦地の図書館 海を越えた一億四千万冊』。
本の力いや、物語の力の大きさをまざまざと見せつけてくれる。
小説ばかりではなくノンフィクションも書いていたのに驚いたのが海猫沢めろん『明日、機械がヒトになる ルポ最新科学』。
さまざまな技術の最前線の人たちにインタビューを行い、そして機械と人とのつながり、それは単純に人が機械をどのように扱うべきなのかというような問題ではなく、機械を人に近づけていくという世界と、人は機械に置き換えるあるいは、人と機械との違いといった哲学的な問題を垣間見せてくれた。
『この恋と、その未来。』は5巻で打ち切りになるはずだったのが、とにかく最終巻まで出せてよかったよ。内容はといえばライトノベルとして文句なしで、ライトノベルとして出すことができたということにも意義があると思う。
2016年12月07日 17:54
『アルファ・ラルファ大通り』コードウェイナー・スミス≫
カテゴリー │ハヤカワ文庫SF
僕がもっとも偏愛している短編小説「アルファ・ラルファ大通り」が収録された短編集である。スミスの短編集は過去にも3冊出ていて、もちろんそれも持っている。それでも僕はスミスの小説を偏愛しているので、出れば買ってしまう。
「アルファ・ラルファ大通り」を読むのはこれで3度目となる。ほとんど再読というものをしない僕にとっては3回も読むというのは今のところ最長不倒距離でもある。
今回はコードウェイナー・スミス全短編集として3冊に分けて出版されるうちの2冊目。スミスの書いた短編の大部分は、一つの共通の歴史の流れの中の一場面を切り取った短編、つまりスミスの描いた未来史を構成する短編ということで、今回の短編集は作中の年代に沿った順番に並べられて編集されている。
ということで2巻目の今回は未来史の中でも一番のトピックでもある、とある出来事を中心とした話が集まっていてそれだけに他の短編と比べて傑作度が高い。
巻頭の「クラウンタウンの死婦人」は中編レベルの分量で読みがいもあるのだが、読み終えてダン・シモンズの<エンディミオン>二部作と似ていると感じた。
スミスの短編はジャンヌ・ダルクの逸話を元にしている。ダン・シモンズのほうも同じく、ジャンヌ・ダルクをベースとしたのか、それとも、<ハイペリオン>シリーズが過去のSF作品のオマージュになっていることを考えると、「クラウンタウンの死婦人」に対するオマージュだったとも考えられる。実際のところは作者に尋ねるしかないけれども、あれこれ想像を巡らせるのは楽しい。
「アルファ・ラルファ大通り」に関しては流石に新しい発見は少ないけれども、再読するたびにこの物語の細部が見えてくる感じがする。
アルファ・ラルファ大通りという言葉や、預言する機械アバ・ディンゴという言葉の響きの良さなんかはなんだかかっこいい。スミスの描く人類補完機構によって管理された社会は、他のSFで描かれたとすればディストピアな社会として描かれるだろうけれども、スミスの手によって描かれるとディストピアに見えないのは、人類補完機構があくまで人類の補完であって完全な管理をしているわけではないからだろう。だからスミスの描く物語に登場する猫は異常なまでに活躍するし、登場人物たちは甘酸っぱいほどの恋をする。
「アルファ・ラルファ大通り」を読むのはこれで3度目となる。ほとんど再読というものをしない僕にとっては3回も読むというのは今のところ最長不倒距離でもある。
今回はコードウェイナー・スミス全短編集として3冊に分けて出版されるうちの2冊目。スミスの書いた短編の大部分は、一つの共通の歴史の流れの中の一場面を切り取った短編、つまりスミスの描いた未来史を構成する短編ということで、今回の短編集は作中の年代に沿った順番に並べられて編集されている。
ということで2巻目の今回は未来史の中でも一番のトピックでもある、とある出来事を中心とした話が集まっていてそれだけに他の短編と比べて傑作度が高い。
巻頭の「クラウンタウンの死婦人」は中編レベルの分量で読みがいもあるのだが、読み終えてダン・シモンズの<エンディミオン>二部作と似ていると感じた。
スミスの短編はジャンヌ・ダルクの逸話を元にしている。ダン・シモンズのほうも同じく、ジャンヌ・ダルクをベースとしたのか、それとも、<ハイペリオン>シリーズが過去のSF作品のオマージュになっていることを考えると、「クラウンタウンの死婦人」に対するオマージュだったとも考えられる。実際のところは作者に尋ねるしかないけれども、あれこれ想像を巡らせるのは楽しい。
「アルファ・ラルファ大通り」に関しては流石に新しい発見は少ないけれども、再読するたびにこの物語の細部が見えてくる感じがする。
アルファ・ラルファ大通りという言葉や、預言する機械アバ・ディンゴという言葉の響きの良さなんかはなんだかかっこいい。スミスの描く人類補完機構によって管理された社会は、他のSFで描かれたとすればディストピアな社会として描かれるだろうけれども、スミスの手によって描かれるとディストピアに見えないのは、人類補完機構があくまで人類の補完であって完全な管理をしているわけではないからだろう。だからスミスの描く物語に登場する猫は異常なまでに活躍するし、登場人物たちは甘酸っぱいほどの恋をする。
2016年09月22日 15:48
5巻以内で完結する傑作漫画99冊+α その三≫
その一
その二の続きです。
その二の続きです。
- 『アクアリウム』須藤真澄
須藤真澄は絶対の安定度を持った漫画家になったと思う。もうどんな作品を描いても一定以上のクオリティが保証されているので安心して読むことができるのだ。
しかし、読者というのは時としてわがままで、安定した作品、つまり面白いことが保証された作品など読みたくなくなることがある。
どこからこの安定が生まれてくるのかは漫画家によってそれぞれ異なるけれども、須藤真澄の場合は視点の変化だと思う。デビュー仕立ての頃の須藤真澄の視点は描かれる作中の人物と同じ視点であり、彼女の描く対象は不安定な心をもった少年少女であった。それゆえに描かれる作品も不安定さをそのまま表現していた。それがいつしか視点が変わり、描く対象と等身大の視点ではなく、作者自身がコントロールするいわゆる神の視点、いやどちらかといえば親としての視点を持ちえて、そしてその視点でもって描くようになった。それが悪いわけではないけれども、時として登場人物と一緒に悲しんだり、泣いたり、笑ったりしたくなる。『アクアリウム』はそれが一番ダイレクトにできる須藤真澄の作品である。。
- 『オンノジ』施川ユウキ
ある日突然、主人公の少女とフラミンゴ以外すべての生き物がいなくなってしまった世界という設定は僕の琴線に触れる設定だ。
長編漫画かと思いきや四コマ漫画で、しかもそこで描かれるのは主人公の日常の風景だ。一人の女の子と一匹のフラミンゴ以外すべての生き物がいなくなってしまった世界という非日常の中で、主人公たちの日常を描いているという時点で何かおかしいうえに、一匹のほうであるフラミンゴも実は人間の男の子で、すべての生き物がいなくなってしまった日に目覚めるとフラミンゴになっていたという設定だ。
どこからつっこめばいいのか、もしくはこんな設定に対して合理的な解決がありうるのか、とかいろいろと思うところも出てくるのだが、しかし読んでいるあいだは作者が仕掛けてくるさまざまなボケの応酬に笑い転げるのに手一杯になるので、ほとんど気にならない。
それでいて時折、不意打ち的にしんみりとした切なくなるような話があったりして、なんかいい話なのだ。そして、このまま非日常の中での日常漫画というままでこの物語が終わってもいいなあと思っているところで話は予想外の場所に着地しする。
- 『増補版 TATSUMI』辰巳ヨシヒロ
「劇画」という言葉の生みの親であり、それまでの漫画の表現方法に劇画という新しい概念をを導入した漫画家の一人。
1980年代以降は日本よりも海外で評価されることが多く、訃報のニュースも日本よりも先に海外のニュースサイトの方が先に報道し、日本ではその真偽が疑われたぐらいである。
辰巳ヨシヒロの絵は、劇画の持つシャープな絵というよりは水木しげるの絵に近い丸っこさがある。劇画でありながら劇画でないというのがおそらく初めて辰巳ヨシヒロの漫画を読んだ時に感じる思いだろう。
しかし、絵柄はどうであれ、そこで描かれている物語、構図、場面の見せ方といったものは少年漫画とは違う世界であり、劇画という概念が生まれたことによって漫画の表現方法や、漫画で描かれる内容が一気に幅広くなったのではないだろうか。
この本は傑作選なのでどの話も捨てがたいのだが強いていえば「地獄」と「グッドバイ」が秀逸。
「地獄」は広島に落ちた原爆を主題とした、とある家の壁に焼きこまれた影の写真をめぐる物語。その影は母親と母親の肩を揉んでいる息子の姿であり、親孝行しているその瞬間に二人は原爆で亡くなったということを意味している。孝行息子の美談の写真として祭り上げられるのだが、その真相は肩を揉んでいるのではなく首を絞めているところだったという驚愕の真相。そしてそこから連なる地獄への道。原爆という地獄の世界が平和な世界へと変わっていっても、主人公はただ一人、地獄を生きているのだというモノローグで終わる。
「グッドバイ」も戦後間もない時代の話で、生きていくために米軍相手に娼婦として生きている女性が主人公。彼女にはアメリカ人の恋人がいて、その彼は彼女に親切で結婚したいと言ってくれるけれども本国には妻がいて、最終的には主人公を捨ててアメリカに帰って行ってしまう。そして彼女に残されたものは、お金がなくなるたびに金をせびりに来る父親だけとなる。しかし、彼女はその父親と寝ることによって全てを捨ててしまおうとする。
読んで楽しくなる漫画ではないが楽しくなるだけの物語が漫画ではない。
- 『ドン・ジョバンニ』福山庸治
『マドモアゼルモーツアルト』の後に描かれた作品で、こちらはモーツァルトが作曲したオペラ、ドン・ジョバンニをほぼそのまま漫画化したものである……が、それはあくまで基本ストーリーの部分だけだ。
主人公ドン・ジョバンニはサムライとして描かれている。では舞台は日本の江戸時代なのかといえば、そうとも言い切れない。ドン・ジョヴァンニの従者レポレッロはなんとロボットである。で、ロボットであるのに江戸の町人風の着物を着ているのだ。たしかに描かれる街並みは江戸時代風、主人公以外の脇役も江戸時代風の衣装を着ているけれども、物語早々にドン・ジョバンニに寝取られそうになるドンナ・アンナは和服ではなくドレスを着ている。つまり和洋入り混じっているうえにロボットまで登場する始末。
なんともまあ作者のやりたい放題、無節操に描かれているかのようにみえるけれども、それ故にか物語全体の雰囲気は軽快で、軽やかで、おそらくは計算され尽くした結果の無節操なのだ。それでいて物語はオリジナルとほぼ同じ展開をしていく。
悲劇で終わるこの物語は、その一方で実は、悲劇か喜劇なのかと論議されることもある。そして福山庸治はラストで独自の着地地点を目指す。実に憎めないドン・ジョバンニなのである。
そしてこの作品においても、コマ割りと構図でもって音を操る技は冴えている。例えばドン・ジョバンニが耳元で大声を出され、耳がキーンとなり何も聞こえなくなってしまうシーンは一見の価値がある。読んでいる此方側も本当にキーンとなり音が消えるのだ。もちろん実際にそうなるのではないのだが、そう錯覚させるだけの力がある。
- 『エイリアン9(1)』富沢ひとし
- 『エイリアン9(2)』富沢ひとし
- 『エイリアン9(3)』富沢ひとし
僕はSFというジャンルが好きなのだが、このSFというジャンルが持つ要素の一つに恐怖というものがある、と思っている。
それは例えば、未知な物にたいする恐怖であり、理解できないということにたいする恐怖であり、コミュニケーションを取ることができないことにたいする恐怖だ。
だから、そういったものを扱ったSF小説などを読んだ時、そこに湧き出てくる感情はワクワクとかドキドキとかではなく恐れだ。富沢ひとしの漫画を読むと感じるのはそういった感情でありそれは富沢ひとしによって描かれるSF的な何かによって生み出される。『エイリアン9』もそうだし、その後に描かれた『ミルククローゼット』全4巻『プロペラ天国』全1巻『特務咆哮艦ユミハリ』全4巻もそうだ。
そしてなおかつ、そんな異質な存在とそれを理解させることのできる表現力でもって描かれた世界と、さらにはそれらを成立させるためのSF的な設定がこれまた輪をかけて異質で、いうなればこれこそワイドスクリーン・バロックだといっても過言ではないと思う。
- 『マフィアとルアー』TAGRO
これまでに三回、出版社を変え、絶版と復刊を繰り返してきた。絶版になるということは売れなくなったということだけれども、復刊するということは読みたいという需要があったということだ。この作品は、読者の人生のある一定の期間だけ必要とする作品なんじゃないかと思う。だから一定の期間を過ぎてしまった人たちにとっては必用の無い物語であり、一定の期間を迎えようとする人にとっては必用な物語なのだ。
もっとも、ここで描かれるのは男の弱さとセンチメンタルさなので、女性には必要のない物語なのかもしれない。
表題作が傑作なのだけれども、梶尾真治の『おもいでエマノン』をモティーフにした「トリコの娘」も捨てがたい。
エマノンは有史以来すべての生き物の記憶を持った女性。だからといって不老不死というわけではなく、記憶が子供に受け継がれていくという形で全ての記憶を持っているのだ。一方、こちらは未来の記憶を持っていると主張する女の子が登場する。しかし実際は過去の記憶を一切持たない女の子だ。では何故彼女は未来の記憶を持っていると言うのだろうか。どう考えても現実的に起こりえないことでありながら、この話はSF的な真相に行き着かない。あくまで現実的に起こりうる真相で、だから全ての真相が明らかになった時、悲しくなる。
この話の中で登場するエマノンの本は高野文子の表紙のバージョンが使われている。
- 『うみべの女の子(1)』浅野いにお
- 『うみべの女の子(2)』浅野いにお
TAGROの『マフィアとルアー』がある年代のある時期だけ必用としながらも普遍性を持ち続けているのに対して、ほぼ同様にある世代のある時期に生きている人しか共感を得ないような作品を描いている浅野いにおの作品は、例えば十年後あたりにどういう受け止められ方をするのだろうか。
そんなふうに思ってしまうのは浅野いにおが描いているのが人だけではなく人を含めた街、登場人物たちが生活している世界を今の風景から切り取って描いているからかもしれない。
浅野いにおの作品であれば『ソラニン』全2巻でもよかったが『ソラニン』全2巻はちょっと綺麗すぎる気がする。もっともっと俗物的で本能的で若さのリビドーに振り回されるまま、自分自身もコントロールできないままに生きていくある世代を、表現規制などものともなしに描いた『うみべの女の子』のほうがもっと切実的で純粋で、そして美しいのだ。連載誌が性表現には規制の緩やかな雑誌だったからこそ描くことのできた作品だ。
まあ、そっちの方面を期待するだけの漫画ではないので、期待してがっかりされても困るのだが。
- 『はるまげ(1)』なにわ小吉
- 『はるまげ(2)』なにわ小吉
殊能将之という作家がいた。『はさみ男』というミステリ小説でメフィスト賞を受賞し作家デビューすることとなったのだが、住所や電話番号等、連絡を取ることのできる内容を書き忘れていために、編集部は雑誌上でこの作家に対して連絡がほしいと呼びかけることをした。
連絡先を書き忘れて応募してしまうということは可能性としては少なからずあるだろうけれども、書き忘れた作品が受賞するとなるとそんなことが起こる確率はかなり少ないだろう。なんでこんな話をしたのかというとこの漫画の作者、なにわ小吉も応募作に連絡先を書き忘れてしまっていたために、編集部が雑誌上で連絡を請う内容を載せたことがあったからだ。
そんなわけだからだろうか、殊能将之にしろ、なにわ小吉にしろ、その作品にはどこかひょうひょうとした、いわば世間ばなれしたものを感じさせる。
で、そんななにわ小吉の作品であればデビュー作であり一世を風靡した、かどうかわわからないけれども、『王様はロバ~はったり帝国の逆襲~』を選びたかったのだが、あいにくとこちらは七巻と巻数が多い。後にリミックス版とし四巻構成のものが出たのでそれでもよかったのだが、四巻構成のものはコンビニ販売専用のものなので入手が難しいので選ぶのをやめた。
『はるまげ』の舞台となるのは、とある原始時代的な文化しかもたない惑星。しかし、主人公は学生服に学生帽をかぶっていて、それでいて学校などというものは存在していなかったりするので、あまり細かいことは考えてはいけない。なにしろギャグ漫画なのだ。
むしろ、あえてもう少し設定について考えてみるとすれば、かつては高度に発達した文明を持った惑星だったけれども、何らかの事情によりその文明が滅び去ってしまった後の世界と考えたほうが辻褄は合いやすいかもしれない。
主人公の弟はありあわせの材料、主に木材とか布だが、それらでもって高度な何かを作り出す。製造過程はまるっきり違うのだが、創りだされるものはロボットだったり、デジカメだったり、全自動洗濯機、もっとも全自動洗濯機の場合は洗濯機という概念が存在しないので、ゴミとして捨てられるのだが、現代社会で普通に使われている道具が生み出され、主人たちはその道具に驚きながらも器用に使いこなす。独特な生態系を持つ惑星を舞台とした少し不思議でかなりシュールなSF漫画なのである。
- 『Spirit of Wonder』鶴田謙二
このあたりで浜松市出身の漫画家も入れておこう。もちろんだからといって無理やり地元出身枠というものを設けたわけではない。5巻以内で完結する傑作漫画を選んでいったらたまたま一人いたというわけである。
ここ数年は新作を発表してくれているけれども、それ以前はめったに漫画を描かない漫画家の一人だった。もっとも、新作を出してくれるからといって、いちファンとして満足しているのかというと微妙なところで、というのもここ数年の新作は物語重視の漫画ではなく、鶴田謙二の絵と世界を楽しむための漫画がほとんどだからだ。
『Spirit of Wonder』で鶴田謙二のファンとなった身としてはやはり『Spirit of Wonder』のような漫画を読みたいのである。
未来の話で、今の世界には存在しない技術やガジェットが登場するけれども、それらを含めて描かれる世界は古臭さを感じる、いわゆるレトロフューチャーの世界。未来の話なのに何処か懐かしく、切なく、それでいて夢と希望を感じさせる世界だ。
老人、特にジジイと呼びたくなるような爺さんがいい味を出して活躍する話が多いのも特徴のひとつで、これからジジイになっていく身としては読んでいて心強い。
- 『夜とコンクリート』町田洋
デビュー作の『惑星9の休日』も捨てがたいが、こちらのほうが完成度が高いと思う。
一コマにおける空間の取り方が実に気持ちよくってこの空間を眺めているだけでも心が満ちた気持ちになることができるのだが、見開きのうまさもあなどれない。
的確な場所で的確な構図でいきなり眼前に広がる一枚の大きな絵は衝撃的だ。
そして、余分なものをとことん削ぎ落したかのようなシンプルな線によって描かれる町田洋の世界はの心地よさは揺るぎない。
もちろん素晴らしいのは絵だけではなく、その絵でもって描かれる物語のほうも素晴らしい。
余分なものをとことん削ぎ落したかのようなシンプルな線によって描かれる町田洋の世界は前作と同様であり、一話の長さが長くなってもその心地よさは揺るぎない。
シンプルな線でありながらも話によってその線のタッチというか線の描き方を変えていて、ある話では人間も物も直線で描かれていたり、ある話では全ての物がフリーハンドっぽい感じで描かれていたり、それらがその物語で描かれる内容とマッチしているかというとそれほどマッチしているわけでもないけれども、ほんの少しだけ感じられる違和感のようなものが、町田洋が描く静かな物語に対する微かなノイズのような味付けとなってより一層、味わいを際立たせている。
- 『営業ものがたり』西原理恵子
『上京ものがたり』『女の子ものがたり』と続く<ものがたり>シリーズの三作目……といふうにも見えるけれども、中身は全く違う。
『上京ものがたり』や『女の子ものがたり』に関する文字通りの西原理恵子自身による営業の話なのだ。『鳥頭紀行』などに代表される毒々しさとふてぶてしさ満載のエッセイとほぼ同じでそこには『上京ものがたり』などでみせたペーソスなどみじんもない。ここまで作者自身の人物像と描かれる作品とがかけ離れているのは珍しいかもしれないが、しかし、そう見えるのは表面的な部分しか見ていないからだ。西原理恵子の作品を読めば読むほど、西原理恵子がどんな作品を描いたとしてもそれは作者自身の人物像とかけ離れてはいないことが見えてくる。
しかし、それはそれとして、ふてぶてしさ満載の営業話の後に突如として、浦沢直樹の『PLUTO』に対する西原理恵子の返歌、あるいは西原理恵子版『PLUTO』である「うつくしいのはら」という短編が
現れると、いくら西原理恵子がこういう漫画を描くということを知っていたとしても驚かされてしまう。「うつくしいのはら」は確かに西原理恵子生涯の最高傑作である。浦沢直樹が『PLUTO』を描かなかったとしたらこの作品は生まれなかったかもしれないことを思うと、浦沢直樹に感謝したい気持ちだ。
ねえ おかあさん
ぼくたちは
いつになったら
字をおぼえて
商売をして
人にものをもらわずに
生きていけるの。
- 『成程』平方イコルスン
女子高生や女子大生たちの日常におけるガールズトークがだらだらと繰り広げられるだけの話で、明確なオチも無いようにみえるが、落ちていないようで落ちているという不思議な世界。彼女たちが生活している世界は、ほぼ現代のごくふつうの世界のようにみえるが、微妙に異なる。どこが異なっているのかについて登場人物や作者によって明確に語られることはないのは、この世界が彼女たちにとっては当たり前の世界で、あらためて読者に説明する必用もないからだ。そもそも会話の流れも必ずしも同じ話題でつながっているわけではなく、突如として関係のない話が割り込んできたりするのはリアルであり、それでいて彼女たちの話が停滞する事なく続くのは、まるでラリーが全く行われないテニスを見ているかのようでもある。ボールを打ち返すことなくただひたすらにサーブだけしているような、それでいてしっかりとテニスの試合が成立しているという不思議さ。そしてときおり会話の中にふつうの女の子ならば使わないだろうと思われる言い回しが現れる。その瞬間だけ、平方イコルスンの少しだけ異なる世界が読み手に現れるのだ。だから物語のオチは最後に登場するのではなく、彼女たちの会話の隙間にオチている。
- 『ポリーナ』バスティアン・ヴィヴェス
アメコミがアメリカの漫画であるのに対して、ヨーロッパの漫画はどんな呼び方をされているのかというと、バンド・デシネあるいはBDと呼ばれている。もっともこれはベルギーとフランスを中心とした地域における呼び名だけれど、フランスという国はそれだけ漫画が盛んな国でもある。さらにはここ数年は日本のアニメや漫画も人気で日本の漫画の影響がバンド・デシネにどういう影響をあたえるのか、はたまた影響などあたえないのか気になるところだが、かりに影響をあたえたとしたら、日本の漫画もうかうかしていられない状況になるかもしれない。実際、日本の漫画の影響を受けた海外の漫画が日本でも翻訳され始めている。さらに日本でも海外の漫画に対してはある程度の評価をする動きもあって文化庁メディア芸術祭ではマンガ部門というものを設け、海外の漫画にも授賞をしている。バスティアン・ヴィヴェスは第十七回文化庁メディア芸術祭マンガ部門で新人賞を授賞した漫画家だ。
バレエをあつかった漫画は少なくはないのだが、日本の場合は踊るということに焦点を当てた話が多い。しかし、この『ポリーナ』はバレエ・ダンサーが主人公で、そして彼女の成長の物語でありながらも、踊るということに焦点はあたっていない。バレエとともに生きていくことの人生全体を俯瞰するかのような形で描かれていく。そこが新鮮だ。
- 『Blow up!』細野不二彦
細野不二彦は職人のような漫画家だと思う。少年漫画でデビューし活躍後、読者層のターゲットを上げ青年漫画へと舞台を移し、そこでも活躍しつづけている。おそらく自分が描くもの、興味を持っているものがどの年齢層にマッチしているのかというものを自覚しているのだろうと思う。最初は『ジャッジ』全2巻を選ぼうかと思ったのだが、あらためて読みなおしてみると作者自身があとがきで、いつか機会があったら描き直してみたいと書いている。物語そのものも完結しているわけでもなく連作短編という、いつでも続きを描くことができる形式でもあるので候補から外した。となると『あどりぶシネ倶楽部』かこの作品のどちらかにするしかなく、描かれた当時の時代的な雰囲気が残っている『あどりぶシネ倶楽部』よりは時代臭の抜けたもう少し普遍的な『Blow up!』の方を選んでみた。
主人公はサックス奏者。それなりに腕はあるけれども一流のサックス奏者になるために名門大学を中退し、日々の生活にも苦労する貧乏な青年。
そして一流を目指しているといっても、自分の才能を信じているわけでもなく、ただ自分の夢だけにしがみついて生きている。しかし、それは決して無様ではなく、生きているということの力強さである。ジャズに関する様々な知識も盛り込まれ、読後、思わずジャズを聞きたくなってしまう。
そしてなによりも、何のために音楽をやるのかという質問に、主人公が最後に見つける答えが素晴らしい。
「自分の生まれた場所より、一歩でも遠くへゆくために」
オリジナルは全2巻だが後に一冊にまとめられた。
- 『ラスト・ワルツ―Secret story tour』島田虎之介
一見、なんのつながりのない短編どうしが読んでいくうちに一つのつながりを見せ、予想だにしなかった地点へと物語が着地するという漫画はこれまでにも何作も描かれてきた。最近だと石黒正数の『外天楼』が記憶に新しい。島田虎之介は寡作ながらもそんな物語を何作も描いてきた漫画家で、『ラスト・ワルツ―Secret story tour』は彼のデビュー作。副題に「Secret story tour」とあるように、誰も語ることのなかった、相互に関連性のなさそうに見える物語を掘り起こし、個々のの小さな物語を語ることによってひとつの大きな物語を語ってみせる。そしてこの大きな物語は、作者のフットボール仲間のエンリケ小林くんが祖父から譲り受けたブラジル製幻のバイク、エルドラドにまつわる物語という作者の身近な場所からはじまり、チェルノブイリ事故で被曝した消防士の話、おならのせいでガガーリンに人類初の宇宙飛行士の座を奪われてしまった男の話と続いていく。そしてなによりも、それらがひとつにまとまっていくのを見守ることができることは大いなる幸せなのだ。
- 『青い空を、白い雲がかけていった』あすなひろし
編集部の意向で別の連載をはじめることになったために物語としては未完のままとなってしまているが、長編ではなく連作短編なので特に問題はない。ただ、最後のページまで辿り着いた時、登場人物たちのその後が気になる。
あすなひろしのその絵は緻密で、どこにも隙のない完成された絵だ。その線はシャープでハッとするくらい鮮やかな絵だ。そして要所要所で登場人物の等身を大胆に変化さる。コミカルなシーンで等身を下げて描く作風は、おなじ漫画家、たがみよしひさの前身ともいえる。おそらくたがみよしひさはあすなひろしの影響を受けていたのではないだろうか。
決して悲しい話ではないのにどこか悲しさが漂っている。これを糸井重里は「真っ昼間の悲しさ」と言い表したのだが、これもまたお見事としかいいようがない表現である。登場人物の、どこか、ここではない場所を求めるかのようなまなざしの一コマがこの悲しさなのひとつなのだろう。
あすなひろしは、登場人物が抱えている悲しみを、明るい場所へと引っ張ってくるのだ。それはおそらく、悲しくても明るい場所で立っていようよという、あすなひろし流のはげまし方なのかもしれない。
- 『東京防衛軍』よしもとよしとも
浅野いにおの系譜を遡っていくと、よしもとよしともにたどり着く。さらに遡ると誰にたどり着くのかはわからないけれども、彼らのスタイルはおそらく1980年代になって生まれたのだろうと思う。
よしもとよしともの作品だと「すきすきマゾ先生」が涙がでるくらい好きで傑作だと思っているけれど、あれはあくまで個人的フェイバリットにしておきたいので、万人向けのこちらの方を選んだ。
よしもとよしともの作品の中ではおそらくもっともバランスのとれた作品だろう。バランスのとれていな作品のほうがよしもとよしともらしさが出ているのだが、僕の好きなSF系の物語であるし、「ウルトラQ」の良質なパロディでもあり、東京を脅かす謎の怪獣たちに対抗する私設東京防衛軍という使命感あふれた設定でありながら、よしもとよしともの世の中を斜めに見るかのような達観した部分がしっかりと出ている。ふざけながらもちょっとだけ、恥ずかしがりながら、まじめに生きている主人公たち。一部トチ狂ったおっさんが登場するけれども、そんな彼らの活躍を見るのは楽しいし、昭和後期から平成初期付近のノスタルジックさもまたいい。
- 『千年万年りんごの子(1)』田中相
- 『千年万年りんごの子(2)』田中相
- 『千年万年りんごの子(3)』田中相
田中相は風通しのよい絵を描く。読んでいて、たとえそこで描かれている内容が重苦しいものであっても、さわやかな風が絵の中を流れ、重苦しさを少しだけ和らげてくれる。
こんなふうに書くと、それは長所ではなく欠点ではないかと思うかもしれないが、欠点ではないのだ。
閉鎖的な村に婿養子に来た主人公。そして、食べてはならないりんごの実を食べてしまったがために、おぼすな様とよばれる神様の嫁としてその身を捧げなくてはならなくなった主人公の妻。
土地に根付く神様の力は、その土地のある範囲のみ影響力があると考えた主人公たちは、その土地を離れ、東京へと逃げることによって、元凶である神様、おぼなす様の影響の範囲から逃れようとする。しかし、その土地に住む人達は全てこの神様の影響の範囲下にあり、おぼなす様の影響はそこに住む子どもたちおよぼし始める。結果、主人公たちは再び村へと戻らざるを得ない羽目になってしまう。
そして主人公の妻は少しづつ若くなっていく。決してハッピーエンドにはならないこの物語を救いのある物語に仕上げているのは、この風通しの良い田中相の絵である。
- 『オトノハコ』岩岡ヒサエ
箱の中には何が入っているのだろうか。
岩岡ヒサエの考える箱の中には音が詰まっていたのである。
空っぽの箱の中には音が詰まっている。
音の表現としての新味こそないけれども、岩岡ヒサエの描く等身の低い、かわいらしいキャラクターたちがいろいろと悩みながらも健気に、いや、健気というよりもけっこうしぶとく成長していく様を見るのは心地よい。
この絵柄というのは岩岡ヒサエの強力な武器で、等身の低いキャラクターのおかげで小さな箱庭の世界を見ているような感覚を受けるし、かわいらしく描かれているから性格もきれいで、描かれる内容も純粋で爽やかなのかというとまったくそうではない。そこで描かれるのは現実と何ら変わりのない世界であり人物で、そんな世界がこの絵で持って描かれるからよりいっそう際立ってみえるのだ。
『花ボーロ』という短篇集には『オトノハコ』の原型短編(前日譚)にあたる短編が収録されている。
- 『九月十月』島田虎之介
島田虎之助からはもう一冊。
『ラスト・ワルツ―Secret story tour』のあと、『東京命日』『トロイメライ』『ダニーボーイ』と、島田虎之助は、ありえたかもしれないもう一つの物語という偽史の物語を発表した。そして『ダニーボーイ』の発表後、しばしの沈黙をする。その間、まったく作品を発表しなかったというわけではなく短編をいくつか発表してはたのだが長編は描かれなかった。そしてその沈黙後に発表された『九月十月』はそれまでの物語とはうってかわって、じつに意欲的な作品だった。それまでの過剰に語る物語は息を潜め、絵の奥底に潜り込んでいる。コマ割りや構図、そこに描かれる絵の中からどこまでその物語を手元に引きずり出すことができるか。読者に挑戦するかのような作品でありながらも、そこで描かれる世界はけっして挑戦的な世界ではなく、それでいて常に読者を不安に導かせようとするある種の恐怖が存在し、そしてこの先、島田虎之介はどこまで行こうとするるのだろうか期待と不安を抱かせる作品だ。
- 『天国の魚』高山和雅
1999年5月に発売された『電夢時空2 RUNNER』以降、新作が発表されることのなかった高山和雅が15年ぶりに発表した新作。
15年のブランクを感じさせない絵と内容はうれしくなるのだけれども、一般受けしそうもないところは少し残念かもしれない。
隕石の落下による津波の被害から逃れるために地下シェルターに避難した五人の男女。津波の衝撃によって意識を失った彼らが意識を取り戻した時、そこで目覚めた世界はなんと1970年代の日本だった。過去にもどったことからこの物語はタイムスリップものかとおもいきや、話が進むにつれて物語は二転三転する。
何処に着地するのか予想もつかない展開と意外な真相そして何よりも物語の結末で描かれる世界から感じとる感覚はSFでなければ感じられることのできない感覚で、久しぶりにこの感覚を得ることのできた漫画だった。登場人物たちの心情や想いを描きつつも情け容赦なくそれらを切り捨ててしまう世界をそのまま共存させて描く。
高山和雅の作品ではこの他に、電子書籍化されている『電夢時空』と『電夢時空2 RUNNER』が入手しやすい。ただし、こちらはタイトルにナンバリングされていながらもそれぞれ全く別のお話なのでどちらから先に読んでもかまわない。
- 『地上の記憶』白山宣之
大友克洋と交流もあり同世代に活躍しながらも寡作で自身の発表した作品を単行本としてまとめることにもあまり興味がなかった白山宣之。
古くは1979年、新しくは2003年に描かれた漫画が収録されている。むろんそれだけの年月が経過しているので絵柄の変化はあるのだけれども、今の視点で見てもなんら遜色ない作品ばかりだ。
小津安二郎の世界を漫画に変換した「陽子のいる風景」や「ちひろ」。時代物の「Picnic」と「大力伝」。とくに「Picnic」のセンスが素晴らしく、表紙は60年代のアメリカ風の絵で、日本の戦国時代の話なのにこんな絵を表紙にしてしまうのが素晴らしい。もちろん内容の方も表紙に負けず劣らず素晴らしいのである。
一番古い「Tropico」は現代の冒険物。もっとも現代といっても描かれたのが1979年なので、今となっては現代とは言いにくい面もある。前編後編というこの本の中では一番のボリュームのある話でありながらも、長編のダイジェスト版のような感じにも感じられるほど紙面が少ないのでちょっと物足りないところが唯一の難点。もっとも昨今のやたらに長過ぎる傾向にある物語に比べれば完結にまとめてしまう潔さがあるので、5巻以内で完結する漫画というくくりの中で取り上げるのにふさわしい漫画だろう。
- 『SKY』六田登
六田登も細野不二彦と同様に少年誌でデビューした後、青年誌へと舞台を移しそこでも活躍をした。
ただその後、六田登はメジャーではない青年漫画誌もしくはその他の雑誌で作品を発表するようになったことを思うと、細野不二彦よりは低迷しているように思われるかもしれない。しかしそれは優劣の問題ではなく、作家性の問題なのだろう。職人である細野不二彦に対して六田登は作家性の強い漫画家なのだ。六田登の描く漫画の主人公は殆どの場合、作中においてかなりの試練を受ける羽目となる。登場人物を悲惨な状況に追い詰めるのは六田登の特徴の一つであり、同時に登場人物の一人に、その作品における主題となる部分を心理学的なアプローチでもって語らせることが多い。そのあたりが好き嫌いの分かれ目で、代表作『F』が一般受けしたのは主人公の設定が破天荒でそして悲惨な状況に追い詰められてもそれを乗り越えていくだろうという安心感を持った主人公だったからだと思う。常に哲学的な主題を抱えている六田登の作品はその主題に見合う紙面でもって描かれるので大長編になることは少ない。
六田登の作品では『遼平新事情』全2巻が好きなんだけれども、今の時代にあの作品が受け入れられるのかというと疑問もあって、それだったらこちらのほうが普遍的だろうということで『SKY』にした。
『SKY』は長編ではなく四つの短編からなる短篇集なのだが、ここでも六田登の哲学的な主題は存在し、四つの短編はその主題にそって描かれ、そして作中の人物によって哲学的にその主題が語られる。そしてもちろんそんな小難しいことを考えずに読むこともできる。六田登の描く世界はどこにでもいる市井の人たちの人生の一瞬を切り取って見せているからだ。
振り返ったその先にある絶対の安心をもたらす笑顔。
心を失ったのではなく、ここにおいてきてしまったのだと捉える気持ち。
逃れようの無い死に対して、自分自身の物語でもってその死を受け止めようとする意志。
そして、遠く遠く大地から離れた場所に見つけたたった一つの言葉。
そんな四つの物語である。
- 『時間の歩き方(1)』榎本ナリコ
- 『時間の歩き方(2)』榎本ナリコ
- 『時間の歩き方(3)』榎本ナリコ
- 『時間の歩き方(4)』榎本ナリコ
当初はシリーズ化の予定がなく、三話で終わる予定だったらしく、話そのものも三話目でひと区切りがついていて、この三話分の話が良くできている。だから一巻だけ読めばいいと思ってしまうのは実は間違い。
続く二巻、三巻で描かれていたエピソードが、最後にきてそうきたかと膝をたたきたくなるくらいにうまいことはまり、作者が希望していたとおりのハッピーエンドに収まる。
タイムパラドックスとそれに対する対処という点においては、パラドックスを起こそうとすると「時間」によって一時停止(ホールド)と呼ばれる現象が発生し、その時間に干渉できなくなるという設定、そしてその状態でさらに時間の定めたルールを犯すとダブルホールドという状態になり、通常の時間の流れとは離された状態になってしまうというのがこの物語における時間の基本設定だ。主人公達は一巻でホールド状態になっており、そしてそのホールド状態を抜けだそうとするというのがそれ以降の話となるのだが、そもそも主人公の一人、杉田果子がホールド状態になってしまったのは、憧れの先輩を助けようとして、先輩の代わりに自分が死んでしまうところをさらに助けてしまったからで、ホールドを解除するということは杉田果子は死んでしまうということになるのだ。
そこで作者は、このアンハッピーエンドにしかならない状況をハッピーエンドに持っていくために残りの三巻をかけて作者は時間のルールを新たに設定しなおし、そこからハッピーエンドに至るロジックをつくりだしたわけで、その手間を思うと多少の疑問や不満は気がつかなかったことにしてもいいかなという気になるぐらい綺麗に収束した物語だ。
- 『サウダージ』カリブsong(作)、田辺剛(絵)
狩撫麻礼、土屋ガロン、ひじかた憂峰、そしてカリブsong等、その他にもまだあるが様々な筆名でもって漫画原作を書いている漫画原作者が田辺剛と組んで発表した一冊。
小泉八雲、カフカ、陶淵明といった古典文学の短編をアレンジした話とオリジナルの話が交じり合った短篇集。原案となった作品名が明記されず、なおかつ原案の短編を読んでいなかったとしたら、どの作品が古典をベースにしたものなのか判別はつかないかもしれない。逆に言えばそれだけオリジナル作品のレベルが高いということでもある。
小泉八雲の日本を舞台とした話である「お貞の話」をベースとした「サヨナラ、また会いましょう」などは舞台を海外のどこかの国に移しながらも物語の展開はほぼ忠実。異国情緒たっぷりに描きながらもそれが破綻しておらず、物語ときれいに融合している。カフカの「断食芸人」をベースとした話も同様で、これを原作の手抜きとみるか、そうではないとみるかで評価が割れるだろうけれども、これは古典文学の見事な翻案だと思う。
2016年09月14日 16:46
『血の極点』ジェイムズ・トンプソン≫
カテゴリー │集英社文庫
かなり高い確率で翻訳されるだろうなとは思っていたけれども、それでも一抹の不安があったジェイムズ・トンプソンの<カリ・ヴァーラー警部>シリーズの4作目が出た。
作者急逝によってシリーズは中断してしまったのは非常に残念なのだけれども、この最後の作品を読み終えてみると、結論からいえばここで終わったとしても文句はない終わり方だった。
一作目は猟奇的な殺人事件を扱って入るものの、警察小説の範囲内に収まる物語だったこのシリーズも巻が進むにつれて、フィンランドという国における社会問題、特に人種差別といった部分に焦点が当たる一方で主人公が警官という立場から逸脱していき、暗黒小説という方向へと進んでいく。そこまでにまでにわずか3巻という分量で、ジェットコースター並のハイペースで主人公は落ちていく。
2巻目の終わりでは主人公に脳腫瘍が見つかり、死ぬかもしれないという状況にまで陥って、3巻ではせっかく治りかけた足の膝も拳銃で撃ちぬかれて杖なくしては歩くこともままならぬ状況に陥ってしまう。もちろんそれだけではない。主人公の奥さんは主人公たちを助けるために犯人を撃ち殺してしまうのだけれどもそのために使ったショットガンの威力が大きすぎて犯人は上半身と下半身が真っ二つ。そのせいだけではないけれども、人を撃ち殺してしまったことが奥さんにとってはPTSDとなり、さらには自分の旦那が警官だと思っていたら証拠隠滅のために死体を酸で溶かして隠滅させることも躊躇しない人物になりさがっていたことで信頼関係を築くことすらできなくなり、別居してしまう。
今回はそんな状況下から物語は始まり、肉体的にも精神的にもボロボロの状態の主人公に対して、更なる追い打ちがかかる。というのも前巻で主人公たちは一千万ユーロという大金を手に入れるのだが、その極秘にしていたことを知った何者かが主人公にたいして脅しをかけてくる。
主人公を恨んでいる人間はそれだけではない。前巻で息子を殺された事業家は暗殺者を雇い、主人公に復讐を企てているし、主人公の上司も主人公が弱みを握っているおかげで手出しはできずにいるけれども、それがなくなれば主人公たちを窮地に陥れようと画策している。
更には奥さんは妻であること、母親であることに対して完全に自身を喪失してしまい失踪し行方不明となってしまう。
そんな状況下において作者はフィンランドにおける人身売買、そして売春という問題をぶち込んで、主人公に重苦しい決断を強いらせて一気に精算させようとする。
結果、主人公に憂いを与える人物は、主人公に敵対する人物はもちろん味方する人物でさえも舞台から退場し、こんな解決の仕方があっていいのだろうかと疑問を抱いてしまうような安息の日にたどり着く。邪魔者はとにかく消し去るのだ。ここまでやるとなると主人公自身もいわゆるダークサイドに落ちてしまうわけだが、しかし、前作ですでに主人公はダークサイドに片足を突っ込んでいて、今回は頭の先まで突っ込むかどうかというだけの問題にすぎない。
お前が死ぬか俺が死ぬかという決断をしなければならないとなればお前が死ねという結論になるのは当たり前のことである。それでも完全にダークサイドに陥れるところまでいかない配慮をしているところがこの作者のにくいところだ。
というわけで、このシリーズもこれが最終作であると考えればハッピーエンドではあるのだが、作者が途中まで書いていたこのシリーズの自作の題名は『Helsinki Dead』。この本の原題が『Helsinki Blood』で、血の次は死である。題名だけで見れば、主人公カリ・ヴァーラー警部の安息の日々はつかの間の日々のようだ。
作者急逝によってシリーズは中断してしまったのは非常に残念なのだけれども、この最後の作品を読み終えてみると、結論からいえばここで終わったとしても文句はない終わり方だった。
一作目は猟奇的な殺人事件を扱って入るものの、警察小説の範囲内に収まる物語だったこのシリーズも巻が進むにつれて、フィンランドという国における社会問題、特に人種差別といった部分に焦点が当たる一方で主人公が警官という立場から逸脱していき、暗黒小説という方向へと進んでいく。そこまでにまでにわずか3巻という分量で、ジェットコースター並のハイペースで主人公は落ちていく。
2巻目の終わりでは主人公に脳腫瘍が見つかり、死ぬかもしれないという状況にまで陥って、3巻ではせっかく治りかけた足の膝も拳銃で撃ちぬかれて杖なくしては歩くこともままならぬ状況に陥ってしまう。もちろんそれだけではない。主人公の奥さんは主人公たちを助けるために犯人を撃ち殺してしまうのだけれどもそのために使ったショットガンの威力が大きすぎて犯人は上半身と下半身が真っ二つ。そのせいだけではないけれども、人を撃ち殺してしまったことが奥さんにとってはPTSDとなり、さらには自分の旦那が警官だと思っていたら証拠隠滅のために死体を酸で溶かして隠滅させることも躊躇しない人物になりさがっていたことで信頼関係を築くことすらできなくなり、別居してしまう。
今回はそんな状況下から物語は始まり、肉体的にも精神的にもボロボロの状態の主人公に対して、更なる追い打ちがかかる。というのも前巻で主人公たちは一千万ユーロという大金を手に入れるのだが、その極秘にしていたことを知った何者かが主人公にたいして脅しをかけてくる。
主人公を恨んでいる人間はそれだけではない。前巻で息子を殺された事業家は暗殺者を雇い、主人公に復讐を企てているし、主人公の上司も主人公が弱みを握っているおかげで手出しはできずにいるけれども、それがなくなれば主人公たちを窮地に陥れようと画策している。
更には奥さんは妻であること、母親であることに対して完全に自身を喪失してしまい失踪し行方不明となってしまう。
そんな状況下において作者はフィンランドにおける人身売買、そして売春という問題をぶち込んで、主人公に重苦しい決断を強いらせて一気に精算させようとする。
結果、主人公に憂いを与える人物は、主人公に敵対する人物はもちろん味方する人物でさえも舞台から退場し、こんな解決の仕方があっていいのだろうかと疑問を抱いてしまうような安息の日にたどり着く。邪魔者はとにかく消し去るのだ。ここまでやるとなると主人公自身もいわゆるダークサイドに落ちてしまうわけだが、しかし、前作ですでに主人公はダークサイドに片足を突っ込んでいて、今回は頭の先まで突っ込むかどうかというだけの問題にすぎない。
お前が死ぬか俺が死ぬかという決断をしなければならないとなればお前が死ねという結論になるのは当たり前のことである。それでも完全にダークサイドに陥れるところまでいかない配慮をしているところがこの作者のにくいところだ。
というわけで、このシリーズもこれが最終作であると考えればハッピーエンドではあるのだが、作者が途中まで書いていたこのシリーズの自作の題名は『Helsinki Dead』。この本の原題が『Helsinki Blood』で、血の次は死である。題名だけで見れば、主人公カリ・ヴァーラー警部の安息の日々はつかの間の日々のようだ。