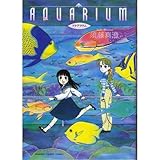2016年09月22日15:48
5巻以内で完結する傑作漫画99冊+α その三≫
その一
その二の続きです。
その二の続きです。
- 『アクアリウム』須藤真澄
須藤真澄は絶対の安定度を持った漫画家になったと思う。もうどんな作品を描いても一定以上のクオリティが保証されているので安心して読むことができるのだ。
しかし、読者というのは時としてわがままで、安定した作品、つまり面白いことが保証された作品など読みたくなくなることがある。
どこからこの安定が生まれてくるのかは漫画家によってそれぞれ異なるけれども、須藤真澄の場合は視点の変化だと思う。デビュー仕立ての頃の須藤真澄の視点は描かれる作中の人物と同じ視点であり、彼女の描く対象は不安定な心をもった少年少女であった。それゆえに描かれる作品も不安定さをそのまま表現していた。それがいつしか視点が変わり、描く対象と等身大の視点ではなく、作者自身がコントロールするいわゆる神の視点、いやどちらかといえば親としての視点を持ちえて、そしてその視点でもって描くようになった。それが悪いわけではないけれども、時として登場人物と一緒に悲しんだり、泣いたり、笑ったりしたくなる。『アクアリウム』はそれが一番ダイレクトにできる須藤真澄の作品である。。
- 『オンノジ』施川ユウキ
ある日突然、主人公の少女とフラミンゴ以外すべての生き物がいなくなってしまった世界という設定は僕の琴線に触れる設定だ。
長編漫画かと思いきや四コマ漫画で、しかもそこで描かれるのは主人公の日常の風景だ。一人の女の子と一匹のフラミンゴ以外すべての生き物がいなくなってしまった世界という非日常の中で、主人公たちの日常を描いているという時点で何かおかしいうえに、一匹のほうであるフラミンゴも実は人間の男の子で、すべての生き物がいなくなってしまった日に目覚めるとフラミンゴになっていたという設定だ。
どこからつっこめばいいのか、もしくはこんな設定に対して合理的な解決がありうるのか、とかいろいろと思うところも出てくるのだが、しかし読んでいるあいだは作者が仕掛けてくるさまざまなボケの応酬に笑い転げるのに手一杯になるので、ほとんど気にならない。
それでいて時折、不意打ち的にしんみりとした切なくなるような話があったりして、なんかいい話なのだ。そして、このまま非日常の中での日常漫画というままでこの物語が終わってもいいなあと思っているところで話は予想外の場所に着地しする。
- 『増補版 TATSUMI』辰巳ヨシヒロ
「劇画」という言葉の生みの親であり、それまでの漫画の表現方法に劇画という新しい概念をを導入した漫画家の一人。
1980年代以降は日本よりも海外で評価されることが多く、訃報のニュースも日本よりも先に海外のニュースサイトの方が先に報道し、日本ではその真偽が疑われたぐらいである。
辰巳ヨシヒロの絵は、劇画の持つシャープな絵というよりは水木しげるの絵に近い丸っこさがある。劇画でありながら劇画でないというのがおそらく初めて辰巳ヨシヒロの漫画を読んだ時に感じる思いだろう。
しかし、絵柄はどうであれ、そこで描かれている物語、構図、場面の見せ方といったものは少年漫画とは違う世界であり、劇画という概念が生まれたことによって漫画の表現方法や、漫画で描かれる内容が一気に幅広くなったのではないだろうか。
この本は傑作選なのでどの話も捨てがたいのだが強いていえば「地獄」と「グッドバイ」が秀逸。
「地獄」は広島に落ちた原爆を主題とした、とある家の壁に焼きこまれた影の写真をめぐる物語。その影は母親と母親の肩を揉んでいる息子の姿であり、親孝行しているその瞬間に二人は原爆で亡くなったということを意味している。孝行息子の美談の写真として祭り上げられるのだが、その真相は肩を揉んでいるのではなく首を絞めているところだったという驚愕の真相。そしてそこから連なる地獄への道。原爆という地獄の世界が平和な世界へと変わっていっても、主人公はただ一人、地獄を生きているのだというモノローグで終わる。
「グッドバイ」も戦後間もない時代の話で、生きていくために米軍相手に娼婦として生きている女性が主人公。彼女にはアメリカ人の恋人がいて、その彼は彼女に親切で結婚したいと言ってくれるけれども本国には妻がいて、最終的には主人公を捨ててアメリカに帰って行ってしまう。そして彼女に残されたものは、お金がなくなるたびに金をせびりに来る父親だけとなる。しかし、彼女はその父親と寝ることによって全てを捨ててしまおうとする。
読んで楽しくなる漫画ではないが楽しくなるだけの物語が漫画ではない。
- 『ドン・ジョバンニ』福山庸治
『マドモアゼルモーツアルト』の後に描かれた作品で、こちらはモーツァルトが作曲したオペラ、ドン・ジョバンニをほぼそのまま漫画化したものである……が、それはあくまで基本ストーリーの部分だけだ。
主人公ドン・ジョバンニはサムライとして描かれている。では舞台は日本の江戸時代なのかといえば、そうとも言い切れない。ドン・ジョヴァンニの従者レポレッロはなんとロボットである。で、ロボットであるのに江戸の町人風の着物を着ているのだ。たしかに描かれる街並みは江戸時代風、主人公以外の脇役も江戸時代風の衣装を着ているけれども、物語早々にドン・ジョバンニに寝取られそうになるドンナ・アンナは和服ではなくドレスを着ている。つまり和洋入り混じっているうえにロボットまで登場する始末。
なんともまあ作者のやりたい放題、無節操に描かれているかのようにみえるけれども、それ故にか物語全体の雰囲気は軽快で、軽やかで、おそらくは計算され尽くした結果の無節操なのだ。それでいて物語はオリジナルとほぼ同じ展開をしていく。
悲劇で終わるこの物語は、その一方で実は、悲劇か喜劇なのかと論議されることもある。そして福山庸治はラストで独自の着地地点を目指す。実に憎めないドン・ジョバンニなのである。
そしてこの作品においても、コマ割りと構図でもって音を操る技は冴えている。例えばドン・ジョバンニが耳元で大声を出され、耳がキーンとなり何も聞こえなくなってしまうシーンは一見の価値がある。読んでいる此方側も本当にキーンとなり音が消えるのだ。もちろん実際にそうなるのではないのだが、そう錯覚させるだけの力がある。
- 『エイリアン9(1)』富沢ひとし
- 『エイリアン9(2)』富沢ひとし
- 『エイリアン9(3)』富沢ひとし
僕はSFというジャンルが好きなのだが、このSFというジャンルが持つ要素の一つに恐怖というものがある、と思っている。
それは例えば、未知な物にたいする恐怖であり、理解できないということにたいする恐怖であり、コミュニケーションを取ることができないことにたいする恐怖だ。
だから、そういったものを扱ったSF小説などを読んだ時、そこに湧き出てくる感情はワクワクとかドキドキとかではなく恐れだ。富沢ひとしの漫画を読むと感じるのはそういった感情でありそれは富沢ひとしによって描かれるSF的な何かによって生み出される。『エイリアン9』もそうだし、その後に描かれた『ミルククローゼット』全4巻『プロペラ天国』全1巻『特務咆哮艦ユミハリ』全4巻もそうだ。
そしてなおかつ、そんな異質な存在とそれを理解させることのできる表現力でもって描かれた世界と、さらにはそれらを成立させるためのSF的な設定がこれまた輪をかけて異質で、いうなればこれこそワイドスクリーン・バロックだといっても過言ではないと思う。
- 『マフィアとルアー』TAGRO
これまでに三回、出版社を変え、絶版と復刊を繰り返してきた。絶版になるということは売れなくなったということだけれども、復刊するということは読みたいという需要があったということだ。この作品は、読者の人生のある一定の期間だけ必要とする作品なんじゃないかと思う。だから一定の期間を過ぎてしまった人たちにとっては必用の無い物語であり、一定の期間を迎えようとする人にとっては必用な物語なのだ。
もっとも、ここで描かれるのは男の弱さとセンチメンタルさなので、女性には必要のない物語なのかもしれない。
表題作が傑作なのだけれども、梶尾真治の『おもいでエマノン』をモティーフにした「トリコの娘」も捨てがたい。
エマノンは有史以来すべての生き物の記憶を持った女性。だからといって不老不死というわけではなく、記憶が子供に受け継がれていくという形で全ての記憶を持っているのだ。一方、こちらは未来の記憶を持っていると主張する女の子が登場する。しかし実際は過去の記憶を一切持たない女の子だ。では何故彼女は未来の記憶を持っていると言うのだろうか。どう考えても現実的に起こりえないことでありながら、この話はSF的な真相に行き着かない。あくまで現実的に起こりうる真相で、だから全ての真相が明らかになった時、悲しくなる。
この話の中で登場するエマノンの本は高野文子の表紙のバージョンが使われている。
- 『うみべの女の子(1)』浅野いにお
- 『うみべの女の子(2)』浅野いにお
TAGROの『マフィアとルアー』がある年代のある時期だけ必用としながらも普遍性を持ち続けているのに対して、ほぼ同様にある世代のある時期に生きている人しか共感を得ないような作品を描いている浅野いにおの作品は、例えば十年後あたりにどういう受け止められ方をするのだろうか。
そんなふうに思ってしまうのは浅野いにおが描いているのが人だけではなく人を含めた街、登場人物たちが生活している世界を今の風景から切り取って描いているからかもしれない。
浅野いにおの作品であれば『ソラニン』全2巻でもよかったが『ソラニン』全2巻はちょっと綺麗すぎる気がする。もっともっと俗物的で本能的で若さのリビドーに振り回されるまま、自分自身もコントロールできないままに生きていくある世代を、表現規制などものともなしに描いた『うみべの女の子』のほうがもっと切実的で純粋で、そして美しいのだ。連載誌が性表現には規制の緩やかな雑誌だったからこそ描くことのできた作品だ。
まあ、そっちの方面を期待するだけの漫画ではないので、期待してがっかりされても困るのだが。
- 『はるまげ(1)』なにわ小吉
- 『はるまげ(2)』なにわ小吉
殊能将之という作家がいた。『はさみ男』というミステリ小説でメフィスト賞を受賞し作家デビューすることとなったのだが、住所や電話番号等、連絡を取ることのできる内容を書き忘れていために、編集部は雑誌上でこの作家に対して連絡がほしいと呼びかけることをした。
連絡先を書き忘れて応募してしまうということは可能性としては少なからずあるだろうけれども、書き忘れた作品が受賞するとなるとそんなことが起こる確率はかなり少ないだろう。なんでこんな話をしたのかというとこの漫画の作者、なにわ小吉も応募作に連絡先を書き忘れてしまっていたために、編集部が雑誌上で連絡を請う内容を載せたことがあったからだ。
そんなわけだからだろうか、殊能将之にしろ、なにわ小吉にしろ、その作品にはどこかひょうひょうとした、いわば世間ばなれしたものを感じさせる。
で、そんななにわ小吉の作品であればデビュー作であり一世を風靡した、かどうかわわからないけれども、『王様はロバ~はったり帝国の逆襲~』を選びたかったのだが、あいにくとこちらは七巻と巻数が多い。後にリミックス版とし四巻構成のものが出たのでそれでもよかったのだが、四巻構成のものはコンビニ販売専用のものなので入手が難しいので選ぶのをやめた。
『はるまげ』の舞台となるのは、とある原始時代的な文化しかもたない惑星。しかし、主人公は学生服に学生帽をかぶっていて、それでいて学校などというものは存在していなかったりするので、あまり細かいことは考えてはいけない。なにしろギャグ漫画なのだ。
むしろ、あえてもう少し設定について考えてみるとすれば、かつては高度に発達した文明を持った惑星だったけれども、何らかの事情によりその文明が滅び去ってしまった後の世界と考えたほうが辻褄は合いやすいかもしれない。
主人公の弟はありあわせの材料、主に木材とか布だが、それらでもって高度な何かを作り出す。製造過程はまるっきり違うのだが、創りだされるものはロボットだったり、デジカメだったり、全自動洗濯機、もっとも全自動洗濯機の場合は洗濯機という概念が存在しないので、ゴミとして捨てられるのだが、現代社会で普通に使われている道具が生み出され、主人たちはその道具に驚きながらも器用に使いこなす。独特な生態系を持つ惑星を舞台とした少し不思議でかなりシュールなSF漫画なのである。
- 『Spirit of Wonder』鶴田謙二
このあたりで浜松市出身の漫画家も入れておこう。もちろんだからといって無理やり地元出身枠というものを設けたわけではない。5巻以内で完結する傑作漫画を選んでいったらたまたま一人いたというわけである。
ここ数年は新作を発表してくれているけれども、それ以前はめったに漫画を描かない漫画家の一人だった。もっとも、新作を出してくれるからといって、いちファンとして満足しているのかというと微妙なところで、というのもここ数年の新作は物語重視の漫画ではなく、鶴田謙二の絵と世界を楽しむための漫画がほとんどだからだ。
『Spirit of Wonder』で鶴田謙二のファンとなった身としてはやはり『Spirit of Wonder』のような漫画を読みたいのである。
未来の話で、今の世界には存在しない技術やガジェットが登場するけれども、それらを含めて描かれる世界は古臭さを感じる、いわゆるレトロフューチャーの世界。未来の話なのに何処か懐かしく、切なく、それでいて夢と希望を感じさせる世界だ。
老人、特にジジイと呼びたくなるような爺さんがいい味を出して活躍する話が多いのも特徴のひとつで、これからジジイになっていく身としては読んでいて心強い。
- 『夜とコンクリート』町田洋
デビュー作の『惑星9の休日』も捨てがたいが、こちらのほうが完成度が高いと思う。
一コマにおける空間の取り方が実に気持ちよくってこの空間を眺めているだけでも心が満ちた気持ちになることができるのだが、見開きのうまさもあなどれない。
的確な場所で的確な構図でいきなり眼前に広がる一枚の大きな絵は衝撃的だ。
そして、余分なものをとことん削ぎ落したかのようなシンプルな線によって描かれる町田洋の世界はの心地よさは揺るぎない。
もちろん素晴らしいのは絵だけではなく、その絵でもって描かれる物語のほうも素晴らしい。
余分なものをとことん削ぎ落したかのようなシンプルな線によって描かれる町田洋の世界は前作と同様であり、一話の長さが長くなってもその心地よさは揺るぎない。
シンプルな線でありながらも話によってその線のタッチというか線の描き方を変えていて、ある話では人間も物も直線で描かれていたり、ある話では全ての物がフリーハンドっぽい感じで描かれていたり、それらがその物語で描かれる内容とマッチしているかというとそれほどマッチしているわけでもないけれども、ほんの少しだけ感じられる違和感のようなものが、町田洋が描く静かな物語に対する微かなノイズのような味付けとなってより一層、味わいを際立たせている。
- 『営業ものがたり』西原理恵子
『上京ものがたり』『女の子ものがたり』と続く<ものがたり>シリーズの三作目……といふうにも見えるけれども、中身は全く違う。
『上京ものがたり』や『女の子ものがたり』に関する文字通りの西原理恵子自身による営業の話なのだ。『鳥頭紀行』などに代表される毒々しさとふてぶてしさ満載のエッセイとほぼ同じでそこには『上京ものがたり』などでみせたペーソスなどみじんもない。ここまで作者自身の人物像と描かれる作品とがかけ離れているのは珍しいかもしれないが、しかし、そう見えるのは表面的な部分しか見ていないからだ。西原理恵子の作品を読めば読むほど、西原理恵子がどんな作品を描いたとしてもそれは作者自身の人物像とかけ離れてはいないことが見えてくる。
しかし、それはそれとして、ふてぶてしさ満載の営業話の後に突如として、浦沢直樹の『PLUTO』に対する西原理恵子の返歌、あるいは西原理恵子版『PLUTO』である「うつくしいのはら」という短編が
現れると、いくら西原理恵子がこういう漫画を描くということを知っていたとしても驚かされてしまう。「うつくしいのはら」は確かに西原理恵子生涯の最高傑作である。浦沢直樹が『PLUTO』を描かなかったとしたらこの作品は生まれなかったかもしれないことを思うと、浦沢直樹に感謝したい気持ちだ。
ねえ おかあさん
ぼくたちは
いつになったら
字をおぼえて
商売をして
人にものをもらわずに
生きていけるの。
- 『成程』平方イコルスン
女子高生や女子大生たちの日常におけるガールズトークがだらだらと繰り広げられるだけの話で、明確なオチも無いようにみえるが、落ちていないようで落ちているという不思議な世界。彼女たちが生活している世界は、ほぼ現代のごくふつうの世界のようにみえるが、微妙に異なる。どこが異なっているのかについて登場人物や作者によって明確に語られることはないのは、この世界が彼女たちにとっては当たり前の世界で、あらためて読者に説明する必用もないからだ。そもそも会話の流れも必ずしも同じ話題でつながっているわけではなく、突如として関係のない話が割り込んできたりするのはリアルであり、それでいて彼女たちの話が停滞する事なく続くのは、まるでラリーが全く行われないテニスを見ているかのようでもある。ボールを打ち返すことなくただひたすらにサーブだけしているような、それでいてしっかりとテニスの試合が成立しているという不思議さ。そしてときおり会話の中にふつうの女の子ならば使わないだろうと思われる言い回しが現れる。その瞬間だけ、平方イコルスンの少しだけ異なる世界が読み手に現れるのだ。だから物語のオチは最後に登場するのではなく、彼女たちの会話の隙間にオチている。
- 『ポリーナ』バスティアン・ヴィヴェス
アメコミがアメリカの漫画であるのに対して、ヨーロッパの漫画はどんな呼び方をされているのかというと、バンド・デシネあるいはBDと呼ばれている。もっともこれはベルギーとフランスを中心とした地域における呼び名だけれど、フランスという国はそれだけ漫画が盛んな国でもある。さらにはここ数年は日本のアニメや漫画も人気で日本の漫画の影響がバンド・デシネにどういう影響をあたえるのか、はたまた影響などあたえないのか気になるところだが、かりに影響をあたえたとしたら、日本の漫画もうかうかしていられない状況になるかもしれない。実際、日本の漫画の影響を受けた海外の漫画が日本でも翻訳され始めている。さらに日本でも海外の漫画に対してはある程度の評価をする動きもあって文化庁メディア芸術祭ではマンガ部門というものを設け、海外の漫画にも授賞をしている。バスティアン・ヴィヴェスは第十七回文化庁メディア芸術祭マンガ部門で新人賞を授賞した漫画家だ。
バレエをあつかった漫画は少なくはないのだが、日本の場合は踊るということに焦点を当てた話が多い。しかし、この『ポリーナ』はバレエ・ダンサーが主人公で、そして彼女の成長の物語でありながらも、踊るということに焦点はあたっていない。バレエとともに生きていくことの人生全体を俯瞰するかのような形で描かれていく。そこが新鮮だ。
- 『Blow up!』細野不二彦
細野不二彦は職人のような漫画家だと思う。少年漫画でデビューし活躍後、読者層のターゲットを上げ青年漫画へと舞台を移し、そこでも活躍しつづけている。おそらく自分が描くもの、興味を持っているものがどの年齢層にマッチしているのかというものを自覚しているのだろうと思う。最初は『ジャッジ』全2巻を選ぼうかと思ったのだが、あらためて読みなおしてみると作者自身があとがきで、いつか機会があったら描き直してみたいと書いている。物語そのものも完結しているわけでもなく連作短編という、いつでも続きを描くことができる形式でもあるので候補から外した。となると『あどりぶシネ倶楽部』かこの作品のどちらかにするしかなく、描かれた当時の時代的な雰囲気が残っている『あどりぶシネ倶楽部』よりは時代臭の抜けたもう少し普遍的な『Blow up!』の方を選んでみた。
主人公はサックス奏者。それなりに腕はあるけれども一流のサックス奏者になるために名門大学を中退し、日々の生活にも苦労する貧乏な青年。
そして一流を目指しているといっても、自分の才能を信じているわけでもなく、ただ自分の夢だけにしがみついて生きている。しかし、それは決して無様ではなく、生きているということの力強さである。ジャズに関する様々な知識も盛り込まれ、読後、思わずジャズを聞きたくなってしまう。
そしてなによりも、何のために音楽をやるのかという質問に、主人公が最後に見つける答えが素晴らしい。
「自分の生まれた場所より、一歩でも遠くへゆくために」
オリジナルは全2巻だが後に一冊にまとめられた。
- 『ラスト・ワルツ―Secret story tour』島田虎之介
一見、なんのつながりのない短編どうしが読んでいくうちに一つのつながりを見せ、予想だにしなかった地点へと物語が着地するという漫画はこれまでにも何作も描かれてきた。最近だと石黒正数の『外天楼』が記憶に新しい。島田虎之介は寡作ながらもそんな物語を何作も描いてきた漫画家で、『ラスト・ワルツ―Secret story tour』は彼のデビュー作。副題に「Secret story tour」とあるように、誰も語ることのなかった、相互に関連性のなさそうに見える物語を掘り起こし、個々のの小さな物語を語ることによってひとつの大きな物語を語ってみせる。そしてこの大きな物語は、作者のフットボール仲間のエンリケ小林くんが祖父から譲り受けたブラジル製幻のバイク、エルドラドにまつわる物語という作者の身近な場所からはじまり、チェルノブイリ事故で被曝した消防士の話、おならのせいでガガーリンに人類初の宇宙飛行士の座を奪われてしまった男の話と続いていく。そしてなによりも、それらがひとつにまとまっていくのを見守ることができることは大いなる幸せなのだ。
- 『青い空を、白い雲がかけていった』あすなひろし
編集部の意向で別の連載をはじめることになったために物語としては未完のままとなってしまているが、長編ではなく連作短編なので特に問題はない。ただ、最後のページまで辿り着いた時、登場人物たちのその後が気になる。
あすなひろしのその絵は緻密で、どこにも隙のない完成された絵だ。その線はシャープでハッとするくらい鮮やかな絵だ。そして要所要所で登場人物の等身を大胆に変化さる。コミカルなシーンで等身を下げて描く作風は、おなじ漫画家、たがみよしひさの前身ともいえる。おそらくたがみよしひさはあすなひろしの影響を受けていたのではないだろうか。
決して悲しい話ではないのにどこか悲しさが漂っている。これを糸井重里は「真っ昼間の悲しさ」と言い表したのだが、これもまたお見事としかいいようがない表現である。登場人物の、どこか、ここではない場所を求めるかのようなまなざしの一コマがこの悲しさなのひとつなのだろう。
あすなひろしは、登場人物が抱えている悲しみを、明るい場所へと引っ張ってくるのだ。それはおそらく、悲しくても明るい場所で立っていようよという、あすなひろし流のはげまし方なのかもしれない。
- 『東京防衛軍』よしもとよしとも
浅野いにおの系譜を遡っていくと、よしもとよしともにたどり着く。さらに遡ると誰にたどり着くのかはわからないけれども、彼らのスタイルはおそらく1980年代になって生まれたのだろうと思う。
よしもとよしともの作品だと「すきすきマゾ先生」が涙がでるくらい好きで傑作だと思っているけれど、あれはあくまで個人的フェイバリットにしておきたいので、万人向けのこちらの方を選んだ。
よしもとよしともの作品の中ではおそらくもっともバランスのとれた作品だろう。バランスのとれていな作品のほうがよしもとよしともらしさが出ているのだが、僕の好きなSF系の物語であるし、「ウルトラQ」の良質なパロディでもあり、東京を脅かす謎の怪獣たちに対抗する私設東京防衛軍という使命感あふれた設定でありながら、よしもとよしともの世の中を斜めに見るかのような達観した部分がしっかりと出ている。ふざけながらもちょっとだけ、恥ずかしがりながら、まじめに生きている主人公たち。一部トチ狂ったおっさんが登場するけれども、そんな彼らの活躍を見るのは楽しいし、昭和後期から平成初期付近のノスタルジックさもまたいい。
- 『千年万年りんごの子(1)』田中相
- 『千年万年りんごの子(2)』田中相
- 『千年万年りんごの子(3)』田中相
田中相は風通しのよい絵を描く。読んでいて、たとえそこで描かれている内容が重苦しいものであっても、さわやかな風が絵の中を流れ、重苦しさを少しだけ和らげてくれる。
こんなふうに書くと、それは長所ではなく欠点ではないかと思うかもしれないが、欠点ではないのだ。
閉鎖的な村に婿養子に来た主人公。そして、食べてはならないりんごの実を食べてしまったがために、おぼすな様とよばれる神様の嫁としてその身を捧げなくてはならなくなった主人公の妻。
土地に根付く神様の力は、その土地のある範囲のみ影響力があると考えた主人公たちは、その土地を離れ、東京へと逃げることによって、元凶である神様、おぼなす様の影響の範囲から逃れようとする。しかし、その土地に住む人達は全てこの神様の影響の範囲下にあり、おぼなす様の影響はそこに住む子どもたちおよぼし始める。結果、主人公たちは再び村へと戻らざるを得ない羽目になってしまう。
そして主人公の妻は少しづつ若くなっていく。決してハッピーエンドにはならないこの物語を救いのある物語に仕上げているのは、この風通しの良い田中相の絵である。
- 『オトノハコ』岩岡ヒサエ
箱の中には何が入っているのだろうか。
岩岡ヒサエの考える箱の中には音が詰まっていたのである。
空っぽの箱の中には音が詰まっている。
音の表現としての新味こそないけれども、岩岡ヒサエの描く等身の低い、かわいらしいキャラクターたちがいろいろと悩みながらも健気に、いや、健気というよりもけっこうしぶとく成長していく様を見るのは心地よい。
この絵柄というのは岩岡ヒサエの強力な武器で、等身の低いキャラクターのおかげで小さな箱庭の世界を見ているような感覚を受けるし、かわいらしく描かれているから性格もきれいで、描かれる内容も純粋で爽やかなのかというとまったくそうではない。そこで描かれるのは現実と何ら変わりのない世界であり人物で、そんな世界がこの絵で持って描かれるからよりいっそう際立ってみえるのだ。
『花ボーロ』という短篇集には『オトノハコ』の原型短編(前日譚)にあたる短編が収録されている。
- 『九月十月』島田虎之介
島田虎之助からはもう一冊。
『ラスト・ワルツ―Secret story tour』のあと、『東京命日』『トロイメライ』『ダニーボーイ』と、島田虎之助は、ありえたかもしれないもう一つの物語という偽史の物語を発表した。そして『ダニーボーイ』の発表後、しばしの沈黙をする。その間、まったく作品を発表しなかったというわけではなく短編をいくつか発表してはたのだが長編は描かれなかった。そしてその沈黙後に発表された『九月十月』はそれまでの物語とはうってかわって、じつに意欲的な作品だった。それまでの過剰に語る物語は息を潜め、絵の奥底に潜り込んでいる。コマ割りや構図、そこに描かれる絵の中からどこまでその物語を手元に引きずり出すことができるか。読者に挑戦するかのような作品でありながらも、そこで描かれる世界はけっして挑戦的な世界ではなく、それでいて常に読者を不安に導かせようとするある種の恐怖が存在し、そしてこの先、島田虎之介はどこまで行こうとするるのだろうか期待と不安を抱かせる作品だ。
- 『天国の魚』高山和雅
1999年5月に発売された『電夢時空2 RUNNER』以降、新作が発表されることのなかった高山和雅が15年ぶりに発表した新作。
15年のブランクを感じさせない絵と内容はうれしくなるのだけれども、一般受けしそうもないところは少し残念かもしれない。
隕石の落下による津波の被害から逃れるために地下シェルターに避難した五人の男女。津波の衝撃によって意識を失った彼らが意識を取り戻した時、そこで目覚めた世界はなんと1970年代の日本だった。過去にもどったことからこの物語はタイムスリップものかとおもいきや、話が進むにつれて物語は二転三転する。
何処に着地するのか予想もつかない展開と意外な真相そして何よりも物語の結末で描かれる世界から感じとる感覚はSFでなければ感じられることのできない感覚で、久しぶりにこの感覚を得ることのできた漫画だった。登場人物たちの心情や想いを描きつつも情け容赦なくそれらを切り捨ててしまう世界をそのまま共存させて描く。
高山和雅の作品ではこの他に、電子書籍化されている『電夢時空』と『電夢時空2 RUNNER』が入手しやすい。ただし、こちらはタイトルにナンバリングされていながらもそれぞれ全く別のお話なのでどちらから先に読んでもかまわない。
- 『地上の記憶』白山宣之
大友克洋と交流もあり同世代に活躍しながらも寡作で自身の発表した作品を単行本としてまとめることにもあまり興味がなかった白山宣之。
古くは1979年、新しくは2003年に描かれた漫画が収録されている。むろんそれだけの年月が経過しているので絵柄の変化はあるのだけれども、今の視点で見てもなんら遜色ない作品ばかりだ。
小津安二郎の世界を漫画に変換した「陽子のいる風景」や「ちひろ」。時代物の「Picnic」と「大力伝」。とくに「Picnic」のセンスが素晴らしく、表紙は60年代のアメリカ風の絵で、日本の戦国時代の話なのにこんな絵を表紙にしてしまうのが素晴らしい。もちろん内容の方も表紙に負けず劣らず素晴らしいのである。
一番古い「Tropico」は現代の冒険物。もっとも現代といっても描かれたのが1979年なので、今となっては現代とは言いにくい面もある。前編後編というこの本の中では一番のボリュームのある話でありながらも、長編のダイジェスト版のような感じにも感じられるほど紙面が少ないのでちょっと物足りないところが唯一の難点。もっとも昨今のやたらに長過ぎる傾向にある物語に比べれば完結にまとめてしまう潔さがあるので、5巻以内で完結する漫画というくくりの中で取り上げるのにふさわしい漫画だろう。
- 『SKY』六田登
六田登も細野不二彦と同様に少年誌でデビューした後、青年誌へと舞台を移しそこでも活躍をした。
ただその後、六田登はメジャーではない青年漫画誌もしくはその他の雑誌で作品を発表するようになったことを思うと、細野不二彦よりは低迷しているように思われるかもしれない。しかしそれは優劣の問題ではなく、作家性の問題なのだろう。職人である細野不二彦に対して六田登は作家性の強い漫画家なのだ。六田登の描く漫画の主人公は殆どの場合、作中においてかなりの試練を受ける羽目となる。登場人物を悲惨な状況に追い詰めるのは六田登の特徴の一つであり、同時に登場人物の一人に、その作品における主題となる部分を心理学的なアプローチでもって語らせることが多い。そのあたりが好き嫌いの分かれ目で、代表作『F』が一般受けしたのは主人公の設定が破天荒でそして悲惨な状況に追い詰められてもそれを乗り越えていくだろうという安心感を持った主人公だったからだと思う。常に哲学的な主題を抱えている六田登の作品はその主題に見合う紙面でもって描かれるので大長編になることは少ない。
六田登の作品では『遼平新事情』全2巻が好きなんだけれども、今の時代にあの作品が受け入れられるのかというと疑問もあって、それだったらこちらのほうが普遍的だろうということで『SKY』にした。
『SKY』は長編ではなく四つの短編からなる短篇集なのだが、ここでも六田登の哲学的な主題は存在し、四つの短編はその主題にそって描かれ、そして作中の人物によって哲学的にその主題が語られる。そしてもちろんそんな小難しいことを考えずに読むこともできる。六田登の描く世界はどこにでもいる市井の人たちの人生の一瞬を切り取って見せているからだ。
振り返ったその先にある絶対の安心をもたらす笑顔。
心を失ったのではなく、ここにおいてきてしまったのだと捉える気持ち。
逃れようの無い死に対して、自分自身の物語でもってその死を受け止めようとする意志。
そして、遠く遠く大地から離れた場所に見つけたたった一つの言葉。
そんな四つの物語である。
- 『時間の歩き方(1)』榎本ナリコ
- 『時間の歩き方(2)』榎本ナリコ
- 『時間の歩き方(3)』榎本ナリコ
- 『時間の歩き方(4)』榎本ナリコ
当初はシリーズ化の予定がなく、三話で終わる予定だったらしく、話そのものも三話目でひと区切りがついていて、この三話分の話が良くできている。だから一巻だけ読めばいいと思ってしまうのは実は間違い。
続く二巻、三巻で描かれていたエピソードが、最後にきてそうきたかと膝をたたきたくなるくらいにうまいことはまり、作者が希望していたとおりのハッピーエンドに収まる。
タイムパラドックスとそれに対する対処という点においては、パラドックスを起こそうとすると「時間」によって一時停止(ホールド)と呼ばれる現象が発生し、その時間に干渉できなくなるという設定、そしてその状態でさらに時間の定めたルールを犯すとダブルホールドという状態になり、通常の時間の流れとは離された状態になってしまうというのがこの物語における時間の基本設定だ。主人公達は一巻でホールド状態になっており、そしてそのホールド状態を抜けだそうとするというのがそれ以降の話となるのだが、そもそも主人公の一人、杉田果子がホールド状態になってしまったのは、憧れの先輩を助けようとして、先輩の代わりに自分が死んでしまうところをさらに助けてしまったからで、ホールドを解除するということは杉田果子は死んでしまうということになるのだ。
そこで作者は、このアンハッピーエンドにしかならない状況をハッピーエンドに持っていくために残りの三巻をかけて作者は時間のルールを新たに設定しなおし、そこからハッピーエンドに至るロジックをつくりだしたわけで、その手間を思うと多少の疑問や不満は気がつかなかったことにしてもいいかなという気になるぐらい綺麗に収束した物語だ。
- 『サウダージ』カリブsong(作)、田辺剛(絵)
狩撫麻礼、土屋ガロン、ひじかた憂峰、そしてカリブsong等、その他にもまだあるが様々な筆名でもって漫画原作を書いている漫画原作者が田辺剛と組んで発表した一冊。
小泉八雲、カフカ、陶淵明といった古典文学の短編をアレンジした話とオリジナルの話が交じり合った短篇集。原案となった作品名が明記されず、なおかつ原案の短編を読んでいなかったとしたら、どの作品が古典をベースにしたものなのか判別はつかないかもしれない。逆に言えばそれだけオリジナル作品のレベルが高いということでもある。
小泉八雲の日本を舞台とした話である「お貞の話」をベースとした「サヨナラ、また会いましょう」などは舞台を海外のどこかの国に移しながらも物語の展開はほぼ忠実。異国情緒たっぷりに描きながらもそれが破綻しておらず、物語ときれいに融合している。カフカの「断食芸人」をベースとした話も同様で、これを原作の手抜きとみるか、そうではないとみるかで評価が割れるだろうけれども、これは古典文学の見事な翻案だと思う。
いろいろな事情と思うところがあってもうひとつブログを作りました。
新しいブログで書いていることは、他愛もない書きなぐりの文章になってしまっていますが、興味のある方は新しいブログの方も見てやってください。
もうひとつのブログ --> abandonné cœur.